東京海上dR GXレポート「カーボンクレジットが産業界へ与える影響 ~シリーズ①「GX-ETSの本格稼働とサステナブルファイナンス」~」
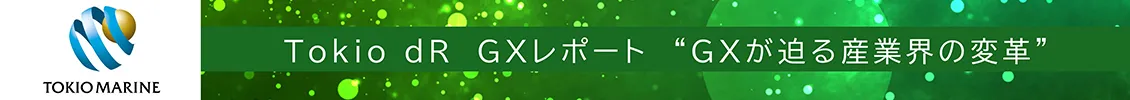
2025/8/18
目次
- GX-ETSについて
- カーボンクレジット市場について
- サステナブルファイナンスの役割
東京海上dR GXレポート「カーボンクレジットが産業界へ与える影響 ~シリーズ①「GX-ETSの本格稼働とサステナブルファイナンス」~」PDF
東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー
脱稿日:2025年8月15日
GX実現に向けて、2026年度から日本初の排出量取引制度「GX-ETS」の本格稼働が始まります。これにより、国内のカーボンクレジット市場は今後、拡大していくことが予想されます。このような状況を踏まえ、カーボンクレジットや排出量取引に関する全体像を総合的に俯瞰し、産業界に与える影響を考察するため、複数回に分けて、有識者へのインタビュー等を実施することとしました。
1回目である今回は、長年、排出量取引をはじめとするサステナブルファイナンスの推進に尽力されてきた吉高まりさん(一般社団法人バーチュデザイン代表理事)と本研究会メンバーとの座談会形式で、GX-ETS稼働に向けたポイントやサステナブルファイナンスの今後について、インタビューを実施しました。

※写真中央が吉高さん、その周囲が本研究会メンバー
1. GX-ETSについて
― 2026年度以降、GX-ETSが法的拘束力を伴う第2フェーズが始まります。2025年度までの第1フェーズについて、どのように総括・評価しますか。
吉高: 第1フェーズは本格運用に向けた気運醸成に非常に効果があったと思います。一方で課題ももちろんありました。参加企業は排出削減の自主目標のみでペナルティもありません。また、主要な全ての企業が参加したわけでもないですし、目標水準にもばらつきがありました。また、報告義務が細かく設定されており、企業からはこれに対する抵抗感があったと聞いています。第2フェーズの制度内容がある程度決まっていて、それに向けた準備としての第1フェーズであれば良かったのでしょう。しかし、企業にとっては情報開示の負担だけが先行した面は否めません。
大場: 「自主的な」取り組みというGXリーグの当初のコンセプト・狙いはどういうものだったのでしょうか。
吉高: 日本は、1997年の京都議定書採択の際、ETSは導入せず、経団連が策定した環境自主行動計画1で成果を上げた経緯があります。当時、日本企業は個社に対して何の削減枠組みが課せられない中で、自主目標を達成するため懸命にカーボンクレジットを購入するなど、海外から見るとユニークな取り組みをしていましたので、それを期待したのかもしれません。パリ協定は、この日本のスタイルと似た、ボトムアップの自主目標が基本ですが、ETSは排出量枠を排出主体に割当て、効率的に排出削減を実現するもので、自主目標を基本としたETSを導入するという構造は効果的に機能しなかった部分があったかもしれません。
― GX-ETS第2フェーズでは、いわゆる「高排出セクター」の企業を対象に排出量取引が義務化されることで、我が国の脱炭素社会の実現に向けて、どのような効果がもたらされると思いますか。
吉高: 排出量取引制度が導入される最大の意義は、限界削減費用(温室効果ガスを追加的に1単位削減するのに必要な費用)を明確化することだと考えます。これまでもアカデミア等では分析されてきましたが、日本では未だによく分かっていないのが現状です。GX-ETSでの価格がその限界削減費用を示す指針になると期待しています。
具体的に一番重要なのは、企業がCO2排出量削減のための投資判断を行う際に、その価格が指針となる点です。そして、企業が排出削減にどれだけの対価を支払う意思があるのかが価格に表れてくるため、金融機関にとっても投融資の予見性が高まります。また、GX-ETSでは排出量に上下限を設けるため、その予見性はさらに高まります。
― 企業側からすると、脱炭素投資の費用対効果を定量化できるメリットに加えて、マクロ的には確実な排出削減が実現できるということですね。
吉高: その通りです。さらに、政府が炭素税のように固定価格で課税するだけではなく、産業界の努力で価格を低下させられる柔軟性も重要です。例えば、英国では、産業界に対して炭素税と排出量取引、どちらかの制度を選択できるようにした結果、後者が選択され、英国は世界初のCO2排出量取引制度導入国となりました。欧米の企業は、一般的に課税を嫌う傾向があります。そのため、自分たちの努力が価格に反映されるフレキシブルな制度を望んだのでしょう。
― 第2フェーズに参加する企業にはどのような行動を期待しますか。単に制度に従うだけでなく、排出量削減に向けた積極的な投資等が期待されるのでしょうか。
吉高: そうですね。現在、インフレや資材・エネルギー価格の上昇が起きている中、GX分野に積極的な投資を促すには第2フェーズ導入のタイミング的に懸念する声もあると思います。しかし、エネルギーの多様化を進める中で、今までのように化石燃料中心の価格をベースにしていては、他のエネルギーへの投資が進みません。やはりカーボンプライスという価格指標があることによって、政府の補助金政策や金融機関の投融資判断に指針が生まれますし、投資家による企業の将来的価値を測る際にもそのプライスが織り込まれていくのではないでしょうか。そのため、企業はそういった状況を踏まえて、投資決定や投資家とのコミュニケーションを行うことが大事になるかと思います。特に電力会社やエネルギー会社にとっては、非常に重要な指針になるでしょう。
― カーボンプライスが企業価値の評価にも反映されていくということですね。企業としては投資だけでなく、リスク管理を含めた戦略の観点も重要になってくるのでしょうか。
吉高: その通りです。第2フェーズにおいて企業は移行計画を提出する必要がありますが、この移行計画の中では将来的な投資計画も考慮されます。政府は移行計画をチェックし、それに基づいて排出枠の割当ても見直していく形になると思います。今回のETS設計の特徴は、とにかく、フレキシブルに運用していくことを重視している点であり、経済状況やエネルギー情勢を見ながら調整していくことになります。そのため、企業は最初に出るプライスを参考にしながら、今後の価格変化に応じて移行計画を見直ししていくことになるのではないかと思います。
― 今後、排出枠の割当方法や、償却方法等の具体的な制度設計が議論されると思いますが、制度上、企業が留意すべき点は何でしょうか。
吉高: まず重要なのは、排出枠割当てに関するベンチマークの算定式ではないでしょうか。現在、発電、製造、その他セクターに分かれたワーキンググループ2が設置され、ベンチマークに関する議論が始まっています。ベンチマークが決まると、次は取引の上限・下限価格の設定に話題が移ると予想します。ベンチマークと上限・下限額の設定、この二つが企業にとって特に注視すべき点でしょう。これら制度の大枠を年内に決定し、2026年4月の第2フェーズの開始に間に合わせるというスケジュールで進んでいます。
研究会メンバー(再生可能エネルギービジネスの実務経験者・有識者。以下同じ。): コングロマリット企業からすると、自社・自グループが展開する事業等のうち、どの範囲がETSの対象になるのか、また一つの業種内でも多様な製品を展開する中でどの部分に注目してベンチマークを設計するかが重要ではないでしょうか。同じ業種でも展開する製品の特性によって、排出削減の難しさが異なるため、不公平感が生じるのではないかと懸念しています。
吉高: 第2フェーズでは、「密接関係者との共同届出」3に関する制度があります。省エネ法の認める範囲内で企業自身が関連会社の範囲を定義して、共同で算定・報告できるようになっています。企業は移行計画や投資計画も提出する必要があるため、一般的にはできるだけ集約したいという考えが働くでしょう。
大場: そうですね。ホールディングス一括で子会社もまとめて計算するのが最適か、分けた方が制度的に有利かという議論はあり得ると思います。
研究会メンバー: 投資計画の一体性という要件は、企業グループ内の共通基盤として投資できる範囲は限られているため、非常に悩ましいところです。グループ内各社で事業内容が異なり、海外に拠点が多い会社や、日本のみに拠点が存在する会社もあるため、関連会社のどこを切り取っていくかはグループ内でも大きな議論になると思います。
― 今の方向性としては、まずはシンプルに制度を作り、問題が出てきたら対応していくということですね。実務上はできるだけ報告をまとめたいというインセンティブが働くかと思います。
吉高: その話以外に私が気になっているのは、省エネ法と高度化法等既存法との関係です。今回のベンチマークと別の対応が必要で、両方コストをかけて対応しなければならない負担があると思います。
研究会メンバー: おっしゃる通り、省エネ法の対応も必要です。グループ全体での排出状況や製品毎のカーボンフットプリント等の情報集約には非常に手間がかかっているため、実務的に大きな課題となっています。現場からすると、一つの情報入力で全ての必要情報が整理できるインターフェースが整備されることが理想ですが、それがない中で複数の法規制に基づく報告へ対応することは大きな負担になります。
吉高: 第2フェーズはまさにその整理段階ではないかと思います。まだ排出枠の割当ては無償、かつ排出枠の10%はカーボンクレジットの使用も可能です。ベンチマークの算定式が決まり次第、既存の法規制との関係も徐々に整理されていくことを期待します。いきなり変えるのは難しいですが、だんだんと収れんしていくべきだと思います。そして、第3フェーズにスムーズに移行できるようにしてほしいと思います。
― 企業のサステナビリティに関する情報開示も最初は複数の基準が存在しましたが、徐々に標準化・統一化が進んでいます。欧州でも議論されているように、産業界に過剰なコストをかけると産業競争力の低下に繋がるので、GX-ETSも他の法規制との整合を図っていくことが望ましいですね。
脚注
1 環境自主行動計画は、経団連が各産業界の自主的な協力のもとに1997年から2014年まで実施した取り組みであり、気候変動(地球温暖化)等に関して、産業別の数値目標を設定しつつ、それに向けた成果・状況を毎年レビューする仕組みで行われました。(参照:日本経済団体連合会「経団連環境自主行動計画の概要」)
2 経済産業省では、セクターごとのベンチマークを決めるため、排出量取引制度小委員会の傘下に製造業ベンチマーク検討ワーキンググループおよび発電ベンチマーク検討ワーキンググループを設置しました。また、他省庁所管の業種(例:運輸)については、当該所管省庁でベンチマークを検討した後に小委員会に報告されると予定されています。(参照:経済産業省「排出量取引制度小委員会(第1回)事務局資料」)
3 改正GX推進法に基づき、企業が直接排出量10万トン以上の密接関係者と共同で排出量目標等を届け出ることを認めています。密接関係者の明確な定義は現在、議論中です。(参照:経済産業省(2025)「排出量取引制度小委員会(第1回)事務局資料」)
2. カーボンクレジット市場について
― GX-ETSの本格稼働に伴い、企業の排出削減努力がより一層求められることになります。その対応策として、今後、カーボンクレジットを導入する企業が増加していくと考えられます。一方で、現時点でのカーボンクレジットの取引対象や取引量はいまだ限定的です。クレジット市場の活性化のために社会的に必要なことは何ですか。
吉高: 第2フェーズでは、排出枠の10%まで認定クレジットが使用可能となりますが、現在流通しているクレジット量は年間100万トン程度のため、全く足りていません。森林系・農業系のクレジットは、地方創生と絡めてストーリーが作りやすいため、クレジット消費企業から好まれる傾向がありますが、これらは特に供給が不足しています。そのため、とにかく供給量を増やしていく必要がありますが、クレジットの質を担保するための方法論や手続きのハードルが高いです。J-クレジットは海外でも通用する質の高いクレジットの組成が求められていますが、日本国内の排出削減に貢献することを目的とするならば、事情の違う海外のクレジットと同等の質を求める必要があるのかは議論の余地があります。
― 現時点では、海外レベルの質を求めると、GX-ETSで生まれる需要を吸収できるほどのクレジット創出は難しいということでしょうか。
吉高: そうですね。農林水産省では、「水稲栽培による中干し期間の延長」4をクレジット創出の新たな方法論として、アジアのスタンダードにしようとしていますが、当該ケースは別として、国内でクレジットを作る際には、国内の排出削減に具体的に利用可能なクレジットも生んでもよいのかと思います。
― 産業界の視点からは、GX-ETSで使用できる一方、国際基準では認められないクレジットを購入することはリスクと感じますか。
研究会メンバー: 基本的には国際的なトップ水準に合わせていくのが大前提です。一方で、クレジット創出プロジェクトを運営・管理できるリソースが国内に限られていることも認識しています。プロジェクトを立ち上げても、それを適切に運営・管理できる主体が少ないことがボトルネックになっているとよく聞きます。
吉高: 確かに私が大学で教えていると、カーボンクレジット・ビジネスに興味を持つ学生は多いのですが、彼らの関心は主に「創出したクレジットをどう使うか」という点に集中しています。クレジット創出のためには、水田やバイオマス発電等の持続可能な運営といった多くのコストと労力が必要です。取引だけのカーボンクレジット・ビジネスに興味を持つ人は多いですが、創出側を増やすのは容易ではありません。
研究会メンバー: もう少し間口を広げることができれば、ビジネスとして参入する主体も増えると思います。例えば、様々な業種がクレジット創出を事業の一部として考えられるようになれば、市場はもっと活性化するのではないでしょうか。
吉高: 大量にクレジット創出が期待される直接空気回収(DAC)、二酸化炭素回収貯留(CCS)ですが、国際的にも方法論等認められておりませんし、技術的にも難しい面があります。私も以前CCSのプロジェクトの方法論策定に関わりましたが、事業のCO2漏洩リスクや永続的なリスク管理等の課題があります。このような排出削減を目指すならば、国内では様々な方法を試行錯誤すべきと考えます。
もちろん、まずは削減努力が重要ですが、私はクレジットの活用には比較的賛成の立場です。補助金だけでは進まない、また、民間資金が回らない、必要な場所に資金が回るのであれば、カーボンクレジットも悪くありません。GX-ETSが始まる際の価格指標としてもカーボンクレジットの価格は重要ですから、様々なタイプのクレジット創出への支援が必要ではないかと思います。
大場: ポテンシャルとして、二国間クレジット制度(JCM)5 の期待値は高いのでしょうか。
吉高: JCMも創出量はまだ少ないですね。他にはパリ協定6条に関するカーボンクレジット6があります。ボランタリークレジット市場に出ている途上国のクレジットの中でパリ協定6条に当てはまるものが出てくるかもしれません。6条クレジットは日本も活用可能であり、第2フェーズにおいて使用できるクレジットにも含まれると思います。
大場: それらに興味を持っている企業もいるのでしょうか?
吉高: いると思います。ただ、JCMは創出にあたって日本政府からの補助7が出ますが、6条に関するクレジットは現時点では日本政府からの組成のための補助ははっきりしていません。どちらかというと、需要側の企業が関心を持っているのではないでしょうか。
脚注
4 「水稲栽培による中干し期間の延長」はJ-クレジットにおける新たな方法論として承認されています。
(参照:農林水産省「J-クレジットにおいて『水稲栽培による中干し期間の延長』が新たな方法論として承認されました!」)
5 二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism; JCM)は、パリ協定6条の規定に基づき、日本が発展途上国等の相手国との間でGHGの排出削減プロジェクトを実施する制度です。このプロジェクトによって生じた排出削減量分のクレジットは日本と相手国で分け合い、プロジェクトに出資した日本企業にもその一部が割当てられる仕組みとなっています。(参照:経済産業省「JCM(二国間クレジット制度)」)
6 パリ協定6条に関するクレジットは、市場メカニズムについて規定する同条に基づき、国際的なGHG排出削減協力により創出される各種のクレジットを指します。(参照:経済産業省「パリ協定6条について」)
7 日本政府は、二国間クレジット制度資金支援事業として、クレジット創出に要する費用について部分的な補助政策を行っています。(参照:環境省「令和7年度二国間クレジット制度資金支援事業のうちシナジー型JCM創出事業の公募開始について」)
3. サステナブルファイナンスの役割
― GXの実現やカーボンニュートラルの達成のためには、排出量取引やカーボンクレジットをはじめとするサステナブルファイナンスの観点がとても重要と認識しています。サステナブルファイナンスは今後、どのような役割を担っていくでしょうか。
吉高: まずサステナブルファイナンスを考える上で、日本の企業の資金調達は、欧米とは異なるということを整理しておく必要があります。日本は、資本市場(直接金融)からの調達が中心の欧米と比較して、銀行(間接金融)の役割が大きいのが特徴です。実際に、GX2040ビジョンに基づく産業立地推進で、地域差はあるものの北海道や九州等で地銀の動きが活発になっています。また、GX推進機構では、これらの金融機関が資金を出しやすいように債務保証、出資、メザニンの提供をします。
GX経済移行債は今後10年間発行されるので、日本の投資家に支えてほしいです。海外投資家がずっと買い続けるかは不透明です。2033年にGX-ETSのオークション導入でエネルギー価格に上乗せされる可能性を鑑み、金融機関にはコスト面だけでなく成長の観点からも企業を評価し、10年程度の中長期視点で投資判断をしてほしいと思います。
― 日本では間接金融の役割が強く、かつ即効性がありますからね。
吉高: そうですね。また、海外投資家の動向も重要です。米国では反ESGの潮流があり、欧州もオムニバス法案の成立8 で情報開示が一部簡素化されるものの、情報開示自体が終わったわけではありません。投資家はデータを高速解析して、よりより投資をするために競争している世界です。開示データが存在する以上、投資家の開示データの活用は今後も続くでしょう。CO2排出量データはいわば会社のエネルギー効率を測る指標ですから、日本においても金融機関がGXを通じてエネルギー効率を評価し、これはひいては日本経済の強さを測る指標にもなると思います。このことを加味して削減貢献量等も評価してほしいところです。
― 中長期的には、CO2排出量が企業や国の評価に反映されるという観点からアクションを取るべきということですね。
吉高: その通りです。ただ、イノベーションを起こす技術をどう評価するかは難しい問題です。企業の資金調達という面では、デット・ファイナンスでは、新技術への大規模な資金供給は容易ではないため、エクイティ・ファイナンス資本市場で新技術を評価・吟味し資金供給してもらう必要があります。それを参考にデット・ファイナンスが動くという循環が重要です。つまり、日本では間接金融が重要とはいったものの、エクイティ・ファイナンスも重要で、この循環が大きくなれば経済と環境の好循環に繋がると期待しています。
脚注
8 オムニバス法案とは、EUにおける企業サステナビリティ報告指令(CSRD)や、企業サステナビリティデューデリジェンス指令(CSDDD)等情報開示に関する規制の簡素化等が盛り込まれた法案です。これによって対象企業の範囲が縮小されるほか、開示基準の簡素化や適用時期の先送り等が行われる内容となっています。(参照:東京海上ディーアール株式会社「CSRDの行方を左右するEUオムニバス法案」)
執筆者プロフィール
東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー
PDFファイルダウンロード
東京海上dR GXレポート「カーボンクレジットが産業界へ与える影響 ~シリーズ①「GX-ETSの本格稼働とサステナブルファイナンス」~」PDF
