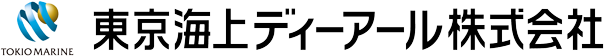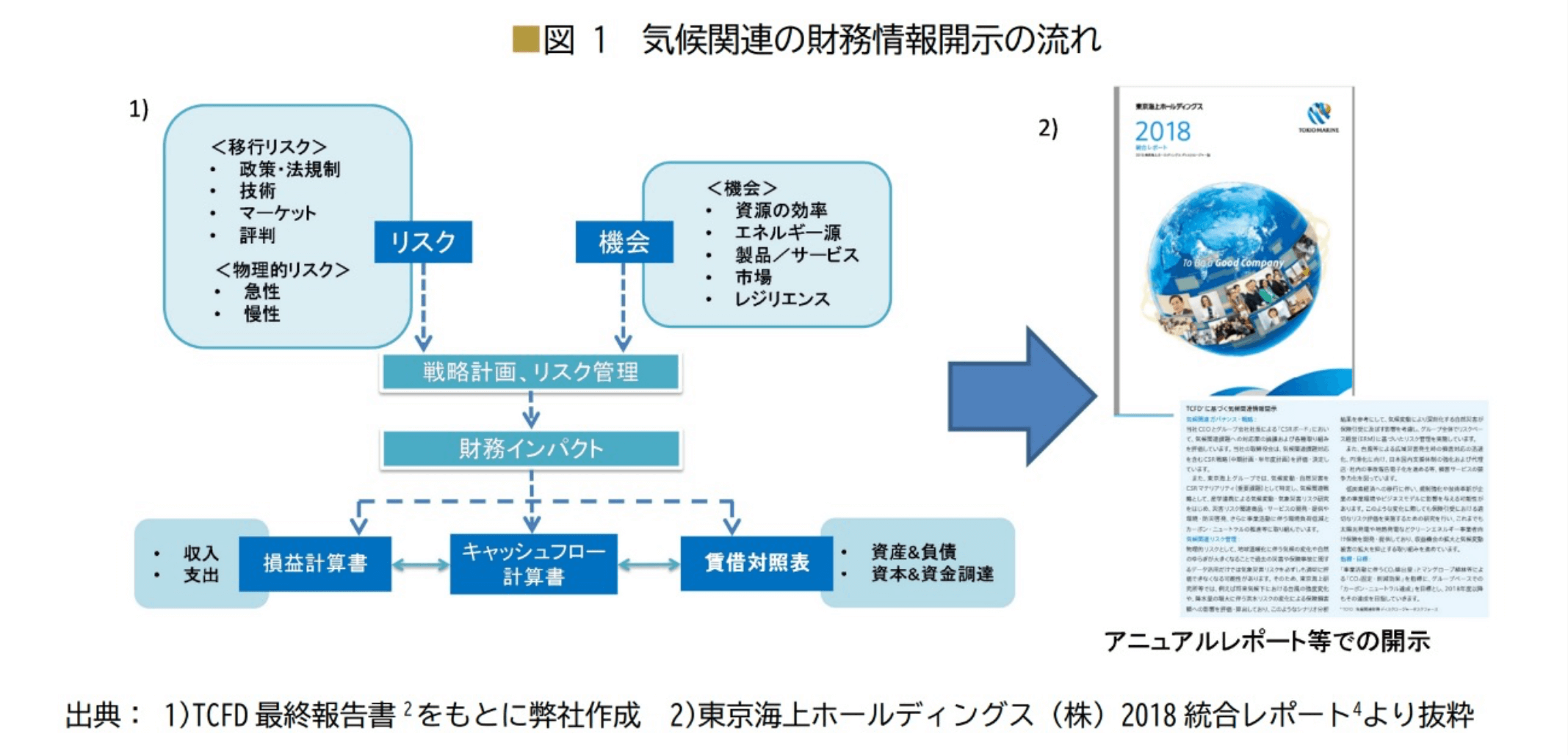事業と仕事紹介
プロジェクトストーリー

Project Story
不測の事態に対応する
計画と体制構築によって
事業を継続する
災害時事業継続支援コンサルティング
OUTLINE
地震・台風・洪水等の自然災害、感染症、事故、インフラ障害、システム障害等の様々な事態によりビジネスが中断、休止することは、企業・組織にとって大きな課題となっている。不測の事態に直面するリスクへ備える重要性が高まり続ける中で、東京海上ディーアールは事業継続や中断した事業の早期復旧を確実に行うための事業継続計画(BCP)の策定をはじめ、事業継続のための取り組みを総合的にサポートしている。
PROJECT THEME
全国に拠点を持つ物流企業。その中でも今回テーマとして取り上げる物流に必要な資機材を扱う企業では、災害時に事業が停止すると業界全体に影響が波及してしまうため、災害時の初動対応とBCPの策定が必要であった。ゼロからの策定に、東京海上ディーアールがどのように関わっていったのか、事業継続のための取り組みをどのように企業に浸透させていったのかを紹介する。

ビジネスリスク本部
マネージャー・主席研究員
津田 喜裕Yoshihiro Tsuda
2007年入社
阪神淡路大震災をきっかけに、大学では防災(水道管の震災被害影響の定量評価)をテーマに研究を行う。新卒で入社した建設コンサルタント会社で通常の道路・交通計画に加えて道路防災にも携わり、企業防災・危機管理に興味を抱く。民間企業におけるコンサルティングにチャレンジできること、誰が何をしているのか、ナレッジをしっかり共有できる規模感に魅力を感じ当社に入社した。

ビジネスリスク本部
マネージャー・主席研究員
小林 亜希Aki Kobayashi
2006年入社
2005年のロンドン留学時にテロが発生。現場にはいなかったものの、普段利用しているバスの路線・地下鉄の駅で被害があり、街の空気は一変。帰国後、就職活動を行う中で、海外リスクマネジメント・テロ対応コンサルティングを提供している当社のビジネスリスク本部(旧:危機管理グループ)に高い関心を持ち入社。また、歴史学を専攻していたことから、過去の事例から学び未来に備えるリスクマネジメントに共感を覚える。
※所属・役職は取材当時の情報です
このプロジェクトではどんな支援を行ったのですか?
初動対応マニュアル・BCP策定支援を行うとともに、単に文書を策定することにとどまらず、クライアントの経営層・従業員に災害対応・危機管理に関する意識を醸成する、総合的な体制構築を支援しました。
基本的な部分も含めてBCPに未着手の企業だったので、私たちが施策を講じるだけでなく、支援を終えた後もBCMのサイクルが回り、対応力が向上し続ける組織になることを目指しました。
BCPの策定は企業によってスタートの状況が異なりますが、このクライアントは施策がなかったものの軽視していたわけではなく、施策の重要性を認識していたからこそ設定できたゴールでもありました。
そうですね。このプロジェクトでは、クライアント内で実務担当者を中心としたBCPの委員会を立ち上げ、一緒に検討していく体制を構築できた点が大きかったと思います。
普段の業務に関する対策のため、外部のコンサルタントがいくら頑張っても業務を熟知するには時間がかかります。業務のことを一番よく知っている方たちが主体的に施策づくりに携わり、私たちがサポートに徹する進め方は、「あなた方のBCPはこれです」と出来上がった施策を渡すより、ずっと意味があったと感じます。

どのようにプロジェクトを進めていったのでしょうか?
まずは1年間で目指すロードマップを策定し、BCPの文書作成と体制構築を同時に進め、最後に訓練を行い検証するという段階を踏みました。
BCPは文書作成だけすれば良いのではなく、どのように実効性を高めていくかがポイントになります。そのために何をすべきか、クライアントと協議しながら進めていきました。
私たちとしては、まずクライアントを理解することから始めました。本社や全国の事業所、物流拠点、そして業務フローをしっかりと見ることで、策定する文書と実態との乖離が生まれないように留意しました。
もし大震災が発生したらどんな被害が考えられるのか、様々な被災シナリオを作成し、停止した業務がどれくらいの期間、どのような影響がどこまで及ぶかといったことまで考え、不足を洗い出していきました。
プロジェクトを進めるにあたっては、クライアントのBCP委員会と定期的に打ち合わせを重ねていきました。ただやはりBCPは「今この瞬間の問題」ではなく「将来起こる可能性がある問題」です。どうやって関係者すべてに問題意識を持ってもらうかは、大きなテーマの一つでしたね。
今回のケースでは、クライアントに危機意識の高い方や積極的に社内に働きかけてくださる方が多かったため、私たちだけでなく、一緒になって策定していこうとする意思を感じられたことは印象深いです。災害対応・危機管理に関する意識を醸成することへの手応えを実感しながら進めることができました。


大変だったことはありますか?
多くの企業でも共通の課題ではあるのですが、本社機能が東京に集約されていることから、リスクを分散させるために地方拠点にどこまで機能を移譲させるのかについて、かなり議論を重ねました。
たしかに、「有事の際に本社機能を地方に移行し、事業継続を図る」と文書に書いてあるだけでは、まったく意味を成しません。どう実行するのか、詳細な施策を検討していきました。
ディテールまで落とさなければ、私たちが支援する意味がありません。本社では手順・役割を細分化し専門部署を設けて日常的に対応している業務であっても、災害時に様々な業務を少人数で対応しなければいけない地方の代替拠点で同じように行うことは実質不可能というケースがどうしても出てきます。
日常的なことをそのまま行うための体制を構築するのではなく、事業を止めないために必要な業務は何かを絞り、それが地方拠点でもできるのか検証を繰り返していきました。
その中でも特殊な業務システムだけは、扱える人員が地方拠点で確保できないという問題があり、地方拠点の方に本社研修に参加していただき、業務システムを扱える人員の育成も進めましたね。

詳細施策を検討した後、どのように浸透させたのでしょうか?
初年度に実施した訓練を、次年度以降も継続して実施したことが一つ挙げられます。初年度の訓練は策定した文書に則る形で進め、有事の際の対策をどのように進めるのかを全社に伝える場でした。次年度以降はより多くの関係者を巻き込み、訓練に参加してもらうことで実効性を高めると同時に、従業員の意識変革を促していきました。
災害時の初動対応は「助け合う」という目的だけでなく、ビジネスを停滞させることなく早期に復帰させることも大切です。日本全体で災害対応への意識やレベルはどんどん上がっており、初動が遅れることでビジネスでも遅れをとってしまいます。だからこそ、日常的に危機管理への意識を高める機会を全社で設ける必要があります。
2年目に行った対策本部訓練では、本社だけでなく営業所も合同で実施し、緊張感をもって訓練することができました。訓練参加者が広範囲になることで、問題点や改善点を洗い出すことにつながり、ブラッシュアップしていくこともできましたね。
そうやって全社的に意識醸成していくことで、私たちの支援が終了しても、自走式で運営できる体制を構築することができました。
私たちが支援を開始し3年目になると、BCP委員会をクライアントだけで運営できるようにもなりましたね。

事業継続計画や体制の構築に関わる意義をどう感じていますか?
今回のケースに限らず常々感じているのですが、私たちがある程度、雛形やスタンダードなモデルを持っていても、クライアントは同じ業界、同じ業種でも、規模も違えば場所も人も違うため、最適化のやり方やポイントもクライアントごとに大きく異なります。今回のクライアントで言えば、何もない状態から危機対策への意識を醸成し、レベルアップしていく過程を伴走する中で、私自身学べることが大いにありました。
物流企業を支援した経験はこれまでありましたが、今回改めて、災害が発生した場合、その地域の拠点だけではなく、被災していない地域のビジネスも同時並行で対策しなければならない重要性を実感しました。何処かの地域が被災しても、同時に他の地域では日常生活が回っていきます。被災地におけるBCPと被災地ではない地域に展開しているビジネスの継続というのは、物流に限らずどの企業にも言えることだと思います。
そうですね。今回のテーマは物流企業ですが、私たちは広範な業界に支援を行っています。私たちの知見を活かした支援をすることで、日本全体の底上げにつながり、社会や産業全体を下支える意義を感じます。
東京海上ディーアールとしてはBCPだけでなく様々なテーマで支援を行っているので、今回のケースを含め、紡いできた信頼をもとに支援の輪を広げていきたいと思います。