東京海上dR GXレポート「オーストラリアのエネルギー政策に関する最新動向」
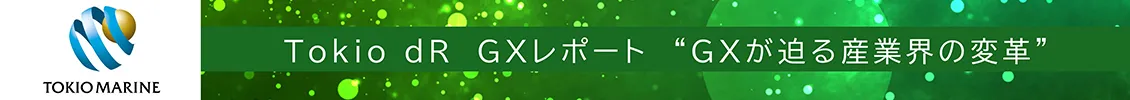
2025/11/11
目次
- はじめに:エネルギー輸出大国である豪州
- 豪州の政策動向
- 日本及び日本企業への示唆
東京海上dR GXレポート「オーストラリアのエネルギー政策に関する最新動向」 PDF
(一財)日本エネルギー経済研究所 資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット
主任研究員 下郡 けい
協力:東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー
脱稿日:2025年11月10日
2025年5月、オーストラリア(以下、豪州)で連邦議会総選挙(下院150議席、上院の半数40議席の改選)が実施され、与党・労働党が地滑り的な勝利を収めました。労働党は少数与党となることが予想されていたものの、実際には下院(定数150)の議席を78から94議席まで伸ばし、単独過半数を確保しています。一方、野党・保守連合(自由党、国民党)は議席を43議席(改選前は55議席)へ減らしました。
2022年5月の総選挙で保守連合から政権交代した労働党は、下院では単独過半数を確保していたものの、上院では過半数に届かず緑の党と政策協定によって政権の安定化を図ってきました。その影響もあり、労働党政権下では、気候変動への取り組みが政策の柱に据えられ、再生可能エネルギーへの移行やグリーン水素の製造・輸出に向けたプロジェクトなどが進められてきました。選挙戦でも、労働党は再生可能エネルギーの拡大とグリーン産業の育成を軸に、段階的かつ継続性のある脱炭素政策を提示しました。一方、保守連合は原子力導入やガス供給の強化を訴えましたが、拙速な原子力導入計画が有権者の警戒感を招き、政策の継続性と社会的受容性の観点から労働党の勝利につながりました。
豪州は世界有数の資源輸出国であり、特に日本は液化天然ガス(LNG)や石炭の多くを豪州から輸入しています。本稿では、日本のエネルギー安全保障を考えるうえで非常に関係の深い豪州について、そのエネルギー政策動向を概説します。なお、本稿ではエネルギーに焦点を当てますが、豪州は重要鉱物(リチウムやコバルト、レアアースなど)の生産国でもあり、日本や米国、欧州などは重要鉱物のサプライチェーン構築にあたって豪州との協力を強化しています。
1. はじめに:エネルギー輸出大国である豪州
豪州には化石燃料資源が豊富に賦存しています。資源の確認埋蔵量は2020年末時点で、原油が24億バレル(世界シェア0.1%、可採年数13.9年)、天然ガスが2.4兆立方メートル(世界シェア1.3%、可採年数16.8年)、石炭が1,502億トン(世界シェア14%、可採年数315年)に達します1。また、2024年の生産量は、石油が36.5万バレル/日(世界第31位)、天然ガスが1,501億立方メートル(世界第7位)、石炭が4.63億トン(世界第5位)と世界の中でも重要なエネルギー生産国です。
また、日本にとっても、豪州はエネルギー供給国としてとても重要な存在です。2023年度には、日本はLNG輸入(総輸入量約6,489万トン)の約41%、石炭輸入(総輸入量約1億6,373万トン)の約65%を豪州から輸入しました2。豪州の最初のLNG輸出は、1989年に生産を開始したNorth West Shelfプロジェクトから日本向けに行われました。同プロジェクトには日本企業(三菱商事と三井物産の合弁事業)が当初から参画し、現在も操業を継続しています。ちなみに、公式記録に残っている両国間の最初の貿易品目は、1865年の石炭とされています。
脚注
1 Energy Institute, “Statistical Review of World Energy”, July 2025.
2 日本エネルギー経済研究所、『EDMCエネルギー・経済統計要覧2025年版』
2. 豪州の政策動向
(1)温室効果ガス削減目標
2022年5月以降の労働党政権では、野心的な目標を掲げつつ気候変動への取り組みを進めています。
連邦政府は、2022年6月に国別貢献(NDC)改訂版を提出し、2030年までに温室効果ガス(GHG)排出量を2005年比で43%削減し、2050年までにネットゼロを達成するという目標を掲げました。これらの目標は、2022年気候変動法で法制化されています。この2030年の目標値は、2013年から9年間続いた保守連合(自由党、国民党)による前政権の目標値(26~28%)を大きく引き上げたものです。2025年9月に発表した新たなNDCでは、ネットゼロに向けた2035年の目標として2005年比でGHG排出量を62~70%削減することが明示されました。
連邦政府によるGHG排出削減に向けた制度として、「セーフガードメカニズム」が挙げられます。同制度は2016年に導入され、年間10万トン以上のGHGを排出する施設3 に対してベースライン(年間排出上限)を設定し、企業に遵守を義務付けるものです。同制度の改正法案が2023年3月に議会で可決され、同年7月から施行されました。改正により、2030年までベースラインより毎年4.9%削減することとなり、この削減率は既存・新規を含むすべての対象施設に適用されます。2030年以降は、5年単位で削減率を設定することになり、2030/31年度から2034/35年度までの削減率は2027年7月1日までに設定される予定です。なお、未達の場合は、クレジットによるオフセットが認められますが、ベースラインの30%以上をクレジットでオフセットする場合には連邦政府(クリーンエネルギー規制局)への報告が必要となります4。
(2)化石燃料(天然ガス、石炭)
天然ガスは、豪州経済や周辺国に対するエネルギー安定供給、エネルギー転換の観点から重要と位置付けられていますが、国内向けのガス供給の不足を中心に課題を抱えています。
豪州では、2016年から2017年にかけて東部においてガス不足が深刻化しました。豪州の在来型天然ガス資源の多くは西オーストラリア州に賦存していますが、ガスの大消費地である東部との間をつなぐパイプラインは敷設されていません(他地域とのパイプライン接続も限定的)。東部のクイーンズランド州では非在来型天然ガスの石炭層メタンガスを開発し、稼働する3つのLNG液化設備5の原料ガスとしていますが、LNGはすべて長期契約に基づいて海外へ輸出されており、国内市場向けに十分なガスを確保することができない状況にあります。また、LNG輸出向けの原料ガスを除く東部や南東部の既存ガス田の生産量は減少傾向にあり、新規供給源の開発が遅れていることなども背景として挙げられます。これを受けて連邦政府は、2017年7月にLNG輸出企業に対して輸出制限を発動する「オーストラリア国内ガス安全保障メカニズム(ADGSM)」を制定しました。ADGSMでは、天然ガスの国内供給が不足すると見込まれる場合に、LNG輸出業者に対して輸出量の制限が課され、輸出許可が必要となります。同制度は当初2023年始めまでを期限としていましたが、2022年7月に2030年まで延長されています。また、2023年4月の改正では、輸出規制発動検討の頻度が従来の1年から四半期ごとに引き上げられました。制度の導入から現在に至るまで輸出規制は発動されていませんが、豪州の国内ガス供給には依然として不安定さが残っています。そのような中で、豪州のガス・LNGプロジェクトには多くの日本企業が参画しており、豪州産LNGの売主でもあり買主でもある日本企業にとって、ADGSMは投資環境の不確実性を高めるものとなっています。
国内ガス供給不足への対応として、連邦政府は2024年5月に「Future Gas Strategy」を策定しました。同戦略では、豪州のガスは国内外のエネルギー移行において重要な役割を果たすと位置付けつつ、既存ガス発見地の開発促進や、インフラの最適化、CCSの促進が盛り込まれました。ただし、具体的な新規ガス田の開発支援策はこれまで明らかになっていません。また、同戦略の中では、連邦政府が掲げるGHG排出削減目標を達成するため、ガスのベント及びフレアリングの削減やガス需要削減策の検討といった取り組みのほか前述のセーフガードメカニズムにも言及されています。改正後のセーフガードメカニズムでは、新規ガス田の排出量目標算定に用いられるベースライン6がネットゼロと定められているため、当該ガス田は操業初日からCO2排出量ゼロを求められることとなります。ガス田開発にはこれまで複数の日本企業も参画していますが、このように厳しいGHG排出規制の下で、CCSの実現可能性などを考慮しつつ、新規投資を検討しなければならない状況にあります。
石炭について、豪州にとって重要な輸出産品であるものの、連邦政府は2050年のネットゼロに向けて環境規制強化を進めており、国内の石炭火力の早期閉鎖を促しています。主要な石炭の生産地であるニューサウスウェールズ州は、石炭産業や石炭火力の役割が大きい点を認識する一方、電源の低炭素化に向けて2030年代後半の石炭火力廃止を決定し、再生可能エネルギーと蓄電池の大規模な導入を進めています。なお、同じく石炭の生産地であるクイーンズランド州においても2025年10月に方針の見直しが発表されるまで(後述)、ニューサウスウェールズ州と同様に2035年までの石炭火力廃止が掲げられていました。
また、前述のセーフガードメカニズムは炭鉱にも適用されるため、2030年頃までは、国内石炭火力向け炭鉱の生産縮小や閉山などが考えられます。今のところ輸出向け炭鉱への影響は少ないとみられていますが7、連邦政府や州政府による環境規制の強化が継続すると、新規炭鉱の開発は困難となり、中長期的には日本への石炭輸出にも影響を及ぼすと考えられます。なお、ニューサウスウェールズ州は、2005年比で2030年までに50%削減、2035年までに70%削減という連邦政府の目標を上回るGHG排出削減目標を設定しており、それに即した独自規制を導入しています。それにより石炭関連でも連邦政府と州政府で二重の厳しい規制がかかることとなり、炭鉱の閉鎖リスクも懸念されているところです。ニューサウスウェールズ州は豪州最大の一般炭8 の輸出州であるため、同州からの石炭供給の減少は、日本を含めた豪州産石炭輸入国に、代替調達先の検討を余儀なくさせる可能性があります。
(3)再生可能エネルギー、電力
2022年以降、連邦政府は、再生可能エネルギーの促進による雇用の創出、電気料金の低減、GHG排出量の削減に重点的に取り組んでおり、電力量に占める再生可能エネルギーの割合を2030年までに82%に引き上げることを目標として掲げています。風力や太陽光といった再生可能エネルギー発電、また蓄電池のようなクリーンかつ系統運用者からの指令に応じて出力調整が可能な容量への投資拡大を促すため、連邦政府は、「容量投資スキーム(CIS)」を2022年12月に導入しました。投資拡大のスピードを加速させるため、CISの支援対象となる発電容量の総量を、2023年11月には9GWから32GWに、2025年7月には32GWから40GWに引き上げています。なお、エネルギー市場オペレーター(AEMO)は2024年6月にネットゼロに向けた「25カ年ロードマップ」を発表しました。AEMOは、石炭火力は2038年までに全て廃止されると引き続き予想し、再生可能エネルギー供給は現在の開発ペースでは不足すると警告したうえで、再エネ転換を支えるための送電網整備への投資増強を求めています。
石炭火力に代わって再生可能エネルギーの導入が進む中で、豪州では、蓄電池の活用が広がっています。全国電力市場(NEM)9では、2016年9月に南オーストラリア州で発生した大規模停電をきっかけに、大型蓄電池の導入が進んでいます。AEMOによると、NEMでは2025年度の設備容量でみると屋根置き太陽光の割合が非常に高く(26%、23,902MW)、石炭火力(17.9%、16,435MW)、風力(14.3%、13,092MW)と続き、蓄電池は2,633MWで2.9%を占めます10。2025年第2四半期の発電量でみると、石炭火力が40.7%、褐炭火力が15.3%、風力が14.1%と続きますが、蓄電池による放電は平均で162MWと前年同期比119%増となり過去最高を記録し、供給量全体の0.7%を占めました。NEMでは太陽光発電の設備容量が大きいことから、卸電力市場では昼間にネガティブプライスが頻繁に発生するようになっていますが、これは充放電で収益を上げる蓄電池事業の拡大にもつながっています。また、蓄電池は、周波数調整市場(FCAS市場)でも存在感を高めており、2025年第2四半期には蓄電池がFCAS市場の54%を占めるに至りました11。蓄電池の活用が進んだのは、NEMにおけるルール整備も影響しています。卸電力市場では、2017年11月のルール改正で2021年10月からのスポット価格を5分ごとに約定することとなりました。これは再生可能エネルギーの導入が進み、価格シグナルに柔軟に対応できる蓄電池やピーク対応の発電設備、デマンドレスポンスが重要性を増した12 ことなどが背景にあります。また、周波数調整市場(FCAS市場)では2023年10月から新たな区分として1秒以内に規定の出力に上下させる「超高速上げ(Very fast raise service)/下げ市場(Very fast lower service)」の運用が開始されました13。これは蓄電池やデマンドレスポンスを念頭に置いたものです。ベースロード電源であった石炭火力の削減と再生可能エネルギーの大量導入が同時に進んだ豪州において系統安定化のために蓄電池を活用する動きは、世界でも特に先進的な取り組みの一つと言えます。
(4)水素
連邦政府は、「オーストラリア国家水素戦略」を策定し(2019年11月策定、2024年9月改訂)、2030年までに同国が水素の世界的プレイヤーとなることを目指して、水素の生産・輸出拠点であり需要集積地でもある水素ハブの創設を戦略の中核に位置付けています。労働党政権では、特にグリーン水素の生産・供給に焦点が当てられ、その実現のためにも上述の再生可能エネルギー導入拡大が進められてきました。2025年5月の総選挙の公約においても新たな水素戦略などは特に発表されておらず、労働党政権下では引き続き現行の水素戦略が前提となると考えられます。2024年9月に改定された水素戦略では、2050年までに年間1,500万トンのグリーン水素を生産し、2030年までに年間20万トンのグリーン水素を輸出するという目標を掲げています。同戦略の柱が、「水素ヘッドスタートプログラム」と「水素製造に対する税優遇措置」です。前者はグリーン水素製造コストと販売価格の値差を10年にわたり支援するもので、後者はグリーン水素製造1kgあたり2豪ドルを補助するものです。これらの連邦政府による措置に加えて、各州は、それぞれの水素戦略を発表するとともに、グリーン水素製造への補助金や支援措置を講じてきました。
しかし、近年、豪州の水素プロジェクトに関して撤退報道が相次いでいます。例えば、クイーンズランド州のGladstone CQ-H2プロジェクトは、日本から関西電力や岩谷産業、丸紅などが参画していましたが、コスト高騰や州政府の追加出資取りやめを受けて中止されました。西オーストラリア州14 やニューサウスウェールズ州15 のプロジェクトはそれぞれ2025年に実施が決定されましたが、豪州におけるグリーン水素の生産・輸出は、コスト高だけでなく支援措置の変更といった困難に直面していると言えます。日本の水素の調達先としても期待される豪州ですが、政策変更や承認手続きの不透明さが、これまで以上にプロジェクトの進展に影響を及ぼす可能性があります。
(5)今後の注目点
2025年9月、連邦政府はNet Zero Planを発表しました。連邦政府は、気候変動を「環境保全と経済成長の両立を図る国家戦略課題」と位置づけ、同計画で2050年までのネットゼロ実現に向けた包括的な道筋を示しています。具体的には、連邦政府が取り組む5つの優先事項として①クリーン電力の拡大、②電化と効率向上、③クリーン燃料利用の拡大、④新技術の加速、⑤炭素除去の拡大を掲げています。例えば①では、風力・太陽光を主力電源化してガス・水力16・蓄電池による系統安定化を図ることや、送電網の刷新に取り組むとしています。また、③では、水素やバイオ燃料、低炭素液体燃料の産業基盤を育成し、国内製造と輸出を両立して燃料安全保障を強化するとしています。
Net Zero Planは2050年までのネットゼロ達成を前提としたバックキャスト方式で構築され、2030年(-43%)、2035年(-62〜70%)を中間マイルストーンとしています。政策・技術・投資の進展を段階的に評価し、ギャップ発生への対策も示されています。現状とのギャップ認識として、例えば電力供給分野では、再生可能エネルギー比率が40%を超えるものの、火力発電の削減や送電網整備が遅延し、許認可手続きがボトルネックとなっています。産業・資源分野では、製鉄・CCUSなど低炭素技術の商用化が遅く、国際競争力の維持が課題です。このようなギャップを実際にどこまで埋めることができるのかが注目されるところです。
一方で、クイーンズランド州政府が2025年10月に発表したEnergy Roadmap 2025では、2035年までに石炭火力を全廃するという方針を公式に撤回し、既存の石炭火力・ガス火力・水力発電所に計16億豪ドルを投資して技術的寿命まで運転を延長すること、再生可能エネルギー導入は継続するものの段階的・現実的なスケジューリングとすることを明らかにしました。クイーンズランド州政府は2024年から保守系が政権の座に就いており、前述したような連邦政府の政策とは方針を異にします。クイーンズランド州が同ロードマップを策定した背景には、再生可能エネルギー導入や送電網整備の遅延、コスト高騰、電力価格高騰にともなう鉱工業の撤退の懸念が挙げられます。これらの課題は他州においても同様であり、従来の野心的な再生可能エネルギー導入目標を維持する他州(例えばニューサウスウェールズ州)への波及効果や、連邦政府と州政府のねじれが各企業の活動にどのような影響を及ぼすのかが注目されます。
脚注
3 鉱山、石油・ガス生産、製造業、廃棄物、運輸部門の施設が対象となる。
4 現在、海外クレジットは利用できない。
5 Australia Pacific LNG(APLNG)、Queensland Curtis LNG(QCLNG)、Gladstone LNG(GLNG)の3カ所。すべてクイーンズランド州に立地する。
6 新規施設(2021年7月1日以降に制度対象となった施設)のベースラインの算定には、排出原単位として「国際ベストプラクティス水準」が適用される。特に新規ガス田は、CCSが利用可能といった理由から、国際ベストプラクティス水準をネットゼロと定めている。(金(2024)「豪州セーフガードメカニズム」、日本エネルギー経済研究所)
7 JOGMEC「豪州における排出量削減に係る制度が及ぼす炭鉱への影響調査」(2024年2月)
8 石炭を用途で分類すると、無煙炭、原料炭、一般炭に分かれる。一般炭は主に発電用ボイラーの燃料として利用される。
9 ニューサウスウェールズ州、首都特別地域、クイーンズランド州、南オーストラリア州、ビクトリア州、タスマニア州を対象。1998年に卸電力市場として開始。
10 AEMO, “Fact Sheet: National Electricity Market”
11 平野学「電力市場における大型蓄電池事業の役割が拡大」『海外電力』(2024年11月)
12 平野学「電気新聞主催海外視察団「豪州で進む大型蓄電池ビジネスとDER活用イノベーション」に参加して~再生可能エネルギー導入に伴う電力市場の課題と多様化する蓄電池の活用策~」『海外電力』(2025年6月)
13 同上。
14 Murchisonグリーン水素プロジェクト:グリーンアンモニアをアジアへ輸出する。
15 Hunter Valley水素ハブ:グリーン水素を製造し、Orica社の低炭素アンモニアや硝酸アンモニウムの生産において原料用天然ガスを段階的に代替。
16 ここには揚水発電も含まれ、現在開発が進められている。既存の水力発電所群(Snowy Scheme、揚水発電所も含まれる)を拡張するSnowy 2.0では、2.2GW/350GWh規模の揚水発電所を新たに建設中である。(Snowy Hydro, “Snowy 2.0”.)
3. 日本及び日本企業への示唆
豪州は、日本にとって重要なエネルギー供給国であると同時に、急速な再生可能エネルギーの拡大を踏まえた先進的な取り組みが注目される国です。日本のエネルギー安全保障の観点では、LNGや石炭を今後も豪州から安定的に調達できるかが大きな関心事となります。総選挙前の労働党政権では、任期後半(2024年から2025年にかけて)に野心的な脱炭素に向けた取り組みと国内ガス不足などの課題とのバランスをとるような動きがみられました。総選挙を経て連邦政府では労働党政権が継続する中で、連邦政府によるGHG排出削減に向けた規制が、化石燃料の投資環境に与える影響を注視する必要があります。特に化石燃料の開発については州政府の規制権限も強いことから、州政府の方針が維持されるのか・変化するのかという点も、現地での日本企業の資源開発や日本向け輸出に影響を及ぼすと考えられます。また、天然ガスについて、豪州国内への供給を十分に増加させる見通しがなかなか立たず、輸出規制が発動される可能性が依然として残る中で、代替調達先の検討が引き続き求められます。加えて、豪州からの水素調達に期待が寄せられているものの、政策変更による水素輸出プロジェクトの中止などが今後も発生する可能性は残されており、日本企業は政策変更のリスクに十分留意する必要があります。
また、連邦政府と州政府の政策にねじれが生まれた結果(例として、連邦と州での方針の相違、連邦と州で二重規制が発生)、企業は連邦と州双方の規制に対応する必要に迫られ、事業のコストや操業リスクが増加しています。政策的な不整合は化石燃料のみならず再生可能エネルギーの投資環境にも大きな不確実性をもたらしており、企業としては投資判断が困難な状況が続く可能性があります。連邦レベルそして州レベルの政策動向の注視が必要です。
一方で、ベースロード電源であった石炭火力の削減と再生可能エネルギーの大量導入が同時に進んだ豪州において系統安定化のために蓄電池を活用する動きは、世界でも特に先進的な取り組みの一つです。蓄電池の戦略的な活用は、再生可能エネルギーの主力電源化を目指す日本の市場制度設計だけでなく、企業が今後の電力ビジネスを検討する上でも参考になると考えられます。
執筆者プロフィール
下郡 けい
(一財)日本エネルギー経済研究所 資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット 主任研究員
