東京海上dR GXレポート「カーボン・クレジットが産業界へ与える影響 ~シリーズ③「GX-ETS義務化による企業経営への影響とカーボン・クレジット戦略へのインプリケーション」~」
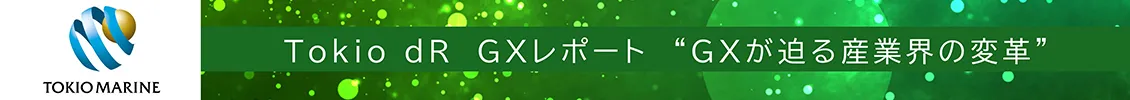
2025/10/30
目次
- GX-ETSの影響
- カーボン・クレジットの活用
- 民間での取組事例
- リスクの類型と管理アプローチ
- 結論
東京海上dR GXレポート「カーボン・クレジットが産業界へ与える影響 ~シリーズ③「GX-ETS義務化による企業経営への影響とカーボン・クレジット戦略へのインプリケーション」~」 PDF
東京海上日動火災保険株式会社マーケット戦略部GX室
柴田 智文
協力:東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー
脱稿日:2025年10月29日
本シリーズでは、国内のカーボン・クレジット市場の動向や産業界に与える影響について、多角的・俯瞰的に考察する連載を実施してきました。第1回では排出量取引をはじめとするサステナブルファイナンスの推進に尽力されてきた吉高まりさん(一般社団法人バーチュデザイン代表理事)にGX-ETS本格稼働に向けたポイント等についてインタビューを行うとともに、第2回では本研究会メンバーの大場がカーボン・クレジット創出の第一人者である有識者へのヒアリングを踏まえた考察を行ってきました。
本シリーズ最終回の第3回では、東京海上グループでカーボン・クレジットに関するサービス開発等を実施しているGX室柴田氏にご寄稿いただき、GX-ETS義務化による企業経営への影響とカーボン・クレジット戦略へのインプリケーションに関する考察を行っていただきました。
1. GX-ETSの影響
(1)炭素に価格の付く時代の到来
2026年度からのGX-ETSの第2フェーズ移行1は、本邦産業界にとって「炭素に価格がつく時代の本格的な到来」を意味します。これは、企業の脱炭素への取り組みが、現状において多く見られるCSRやブランディングといった側面に留まらず、リスク・機会の両面で企業収益に直接的かつ大規模な影響を及ぼす経営課題へと移行する、重大な転換点であると言えます。
(2)リスク:GHG排出という新たなコスト
GX-ETSの第2フェーズ以降、Scope1の排出量が一定規模(10万t以上)を超える企業には排出量取引制度への参加が義務付けられます2。これにより、企業の削減目標が未達となる場合、その未達分について、当該企業は原則GX-ETSを通じ排出枠を購入して補填する必要が生じます。
このインパクトは決して小さくありません。例えば、電力・鉄鋼・化学等大規模なGHG排出を伴う業界の大手企業を例に取れば、制度設計次第ではあるものの、仮に削減目標対比10%程度の未達が生じ、それを排出枠購入により調達しようとした場合、その購入のためのコストは数百億円規模(炭素価格が本稿執筆時点の価格水準の5,000円/t3程度で推移すると想定)となります。
特に、鉄鋼・化学等の排出削減が困難な所謂Hard-to-Abateに分類される業界においては、省エネや燃料転換のための設備改修に長期間と巨額の設備投資が必要となります。このため、削減目標未達と排出枠の価格上昇は、企業の利益水準に長期かつ重大な影響を与えるリスクファクターとなります。
(3)機会:プロフィットセンターとしての脱炭素
一方で、GX-ETSは、新たなビジネスチャンスも創出します。他社に先駆けてGHG削減を進め、国の削減目標を上回る成果を上げた企業は、そのGHGの超過削減分をGX-ETSで売却し収益化することが可能となります。加えて、GX-ETSにおいては削減目標の達成に同制度で活用可能な適格カーボン・クレジットの活用が認められる見込み4 であるため、企業は省エネ技術の普及、植林・森林保護、CCS(二酸化炭素回収・貯留)といったカーボン・クレジット創出プロジェクトの実施を通じてJ-クレジットやJCMクレジットを創出し、新たな収益源とするなど、義務化を契機とした攻めの脱炭素戦略の構築も期待できます。
また、カーボン・クレジットに関する取引市場の環境も急速に改善しつつあります。東京証券取引所のカーボン・クレジット市場では、国際イニシアチブ(RE100等)で活用可能な再エネ由来のJ-クレジット価格が近年高騰5し、省エネ由来等の他クレジット価格を牽引しています。現状の国際イニシアチブ対応に向けた需要増加に加えて、GX-ETSという公的制度における義務達成目的の買い手(オフテイカー)が長期的に存在するという見通しは、市場の需要減少や価格下落といったリスクを大幅に緩和する役割を果たすものと期待されています。
従来、カーボン・クレジット市場は、限定的で不安定な需要による流動性への懸念と、それゆえの価格下落リスクが市場参加者にとって重大なリスク要因と見做されてきました。それらのリスクに対し、上記のクレジットを取り巻く情勢変化や、経済産業省および東京証券取引所によるマーケットメイカー制度の導入等、流動性改善に向けた官民の努力6により、多くの市場参加者が安心して取引に参加できる土台が整いつつあります。
(4)経営への示唆:炭素価格を織り込んだ投資意思決定
GX-ETSの第2フェーズ移行は、企業の排出削減に関する取り組みの位置付けをCSR主体の活動から、あらゆる事業・投資計画における収益・原価改善のための活動へ転換させます。そのため、脱炭素投資を単なる「環境対策コスト」として捉えるのではなく、将来の自社プロジェクトごとの排出量と炭素価格の予測値を事業の採算性評価に組み込む「インターナル・カーボンプライシング(ICP)」7 の考え方が戦略検討において有益となります。
GX実行に向けた政策を議論する内閣総理大臣を議長とするGX実行会議(第7回)8の政府提出資料において、日本エネルギー経済研究所(IEEJ)等による将来の炭素価格の試算が示されています9。同研究所は2050年度の排出量取引制度の有償オークションの価格を約83-131ドル/tと試算していますが、このような長期的な価格上昇を前提とすれば、エネルギー多消費型産業が大型の設備投資を検討する際、将来の炭素価格は、資源・エネルギー価格等と並ぶ最重要変数の一つとなります。
現在のJ-クレジット価格水準10であっても、考慮漏れはプロジェクトの採算性を悪化させかねません。ましてや、IEEJの試算通りの価格上昇が起これば、プロジェクトの割引現在価値(DCF法による現在価値)に対し、採算性を大きく左右するインパクトを持つ可能性があります。GX-ETSの導入は、すべての企業に対し、機会とリスクの両面から自社の事業戦略を再評価することを迫っています。
現在GX-ETSの対象は排出量10万tと大企業が中心であるものの、政府による検討経緯を踏まえれば排出量の閾値が引き下げられる可能性11もあり、現時点で義務化対象外の企業であっても中長期戦略における機会・リスク両面のシナリオにおいて炭素価格による影響を織り込むことは経営計画を蓋然性の高いものとする上で重要となります。
脚注
1 経済産業省HP,「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」,P6
2 同上
3 日本取引所HP,「カーボン・クレジット市場日報」
4 経済産業省HP,「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」,P21
5 日本取引所HP,「カーボン・クレジット市場日報」
6 日本取引所グループHP,「カーボン・クレジット市場におけるマーケットメイカー制度の導入について (制度要綱の公表等)」
7 環境省HP,「インターナル・カーボンプライシングについて」, P3
上記資料において「企業内部で見積もる炭素の価格であり、企業の低炭素投資・対策を推進する仕組み」と定義されています。「気候変動関連目標(SBT/RE100)に紐づく企業の計画策定に用いる手法であり、省エネ推進へのインセンティブ、収益機会とリスクの特定、あるいは投資意思決定の指針等として活用される」との記載のとおり、GX-ETSへの参加義務化を見据えて、企業側では中長期にわたる投資検討において、将来の炭素価格の想定値を踏まえた検討を行うことが、将来の炭素価格上昇に対する有効な備えとなるものと考えられます。
8 内閣官房HP,「GX実行会議の開催について」
9 内閣官房HP, GX実行推進担当大臣提出資料,「我が国のグリーントランスフォーメーション実現に向けて」,P35
なお、同試算値は、日本エネルギー経済研究所「20兆円の歳入を生むカーボンプライス」(2023年7月25日公表)より引用し2023年8月時点の為替ベースで米ドルに換算したものです。同レポートの試算前提は政府が起債する20兆円のGX経済移行債をカーボンプライシングによる歳入を原資として償還する場合に必要となる炭素価格であり、財政均衡の観点で望ましい炭素価格の観点である点で有力な試算値であると考えられます。
10 クレジットの分類や時期により異なるが、2025年9月現在5,000円/t前後の価格が中心価格帯となっています。日本取引所HP,「カーボン・クレジット市場日報」
11 GXリーグ設⽴準備事務局HP,「来年度から開始するGXリーグにおける排出量取引の考え⽅について③」,P9
当該資料において「国内直接排出量10万tCO2以上という閾値は、企業の取組状況等をふまえ、第2フェーズ以降に引き下げる可能性もある。」との記載があります。
2. カーボン・クレジットの活用
前述の議論のとおりGX-ETSの本格稼働は、カーボン・クレジットの活用目的を根底から変える可能性があります。これまで一部の先進企業においてサステナビリティ部門主導で実行されてきたCSRやブランディング目的のカーボン・クレジットの「自主的な活用」から、2026年度以降はGX-ETSにおける削減目標の達成というコスト管理に直結する経営戦略の一部としての「コンプライアンスのための活用」の比重が増すこととなります。
(1)経営課題としてのクレジット調達
自主的な活用の段階では、カーボン・クレジットの調達は主に企業のブランドイメージ向上が主目的でした。しかしながら、GX-ETS対応としてのコンプライアンス目的が重みを増す場合、経営企画部門とサステナビリティ部門が連携し、より複合的な視点でクレジットと向き合うことが必要となります。具体的には、従来のクレジットの「①品質」という要素に加え、「②コスト」や「③供給安定性」といった要素が検討の重要要素として加わることとなります。
既に欧米や本邦においても先進企業の一部は、社内にカーボン・クレジット専門の調達・品質管理チームを組成し、リスクマネジメントを含めた検討を推進していますが、同様の動きは今後本邦の他の企業においてもより本格化するものと考えられます。
先進企業の中には、需要家としてカーボン・クレジットを購入するだけでなく、価格安定化と供給安定性の確保を狙い、カーボン・クレジットの生産者(デベロッパー)との長期購入契約(オフテイク)やプロジェクトへの共同出資、さらには自社での案件開発(プロシューマー化)に乗り出す事例も現れていますが、これらは、クレジットを単なるコストではなく、新規事業として新たな収益源へと転換することを目指す戦略的な行動であると言えます。
(2)カーボン・クレジットによる炭素価格リスクの戦略的ヘッジと先行者利益の獲得
GX-ETSの参加が義務付けられる2026年度以降、カーボン・クレジットは自社努力だけでは削減しきれない排出量を補う、いわば保険のような役割を持つと考えられます。仮に将来の炭素価格が前述のIEEJが示すような価格水準で推移した場合、排出削減の未達は企業にとって重大な経営リスクとなることから、将来の炭素価格上昇リスクへの戦略的なリスクヘッジの手段として、カーボン・クレジットの重要性は増大することとなります。
カーボン・クレジット分野の先進的企業の多くは、当初から大規模な投資に乗り出すのではなく、段階的なアプローチを取ることでリスクを制御しながらケイパビリティ獲得を進める以下のようなケースが一般的です。
| ① | スモールスタート: まずは少量のクレジットを購入し、方法論や市場のプレイヤー、契約実務といった知見を蓄積。 |
| ② |
ナレッジの活用: 次に、その過程で得た情報網を活かし、有望なプロジェクトとの長期契約や、研究開発目的での少額出資を行う。 |
| ③ |
事業化: 最終的に、そこで培った能力を基に、自社での大規模なクレジット創出案件開発へと駒を進める。 |
上記のように段階的な取り組みを採用することで、企業は自ら獲得した知見において許容可能な範囲内に戦略的リソース(人的資源・戦略投資額等)の投入量を調整することが可能であることから、リスク最小化が可能で、取り組みによるデメリットは限定的であると考えられます。
一方で、Bloomberg New Energy Financeによる試算では、シナリオにより幅があるものの2050年時点のカーボン・クレジット市場の市場規模が現在の数十倍から数百倍に拡大する試算が示されており12、一定市場が成長軌道に乗った将来時点において必要に迫られる形で拙速に本分野に関する検討を行うことはリスクを高める恐れがあります。現状のカーボン・クレジット市場は比較的買い手市場の環境にあり、国内外の最有力デベロッパーにアクセスし優良プロジェクトや主要プレイヤーと関係構築を行うことは容易ですが、市場が拡大した将来時点において、それらのプロジェクトやプレイヤーにアクセスすることは、現在より格段に困難となることが予想されます。
このように、現在黎明期にあるカーボン・クレジット市場においては、早期に関与することでリスクを制御しながら知見やネットワーク等の「先行者利益」を享受できる可能性がある一方、将来有力マーケットとなることが確実視された時点からの参入では、知見や情報源となるネットワークを欠いた状態で高騰したカーボン・クレジットの調達や不利な条件でプロジェクト投資を迫られるリスクが懸念されます。
(3)逼迫する需給と競争の激化
GX-ETSでは、義務履行に使えるクレジットが排出量の10%に制限される予定です13。しかしながら、多くの対象企業がこの上限に近い量のクレジット活用を選択した場合、市場の需給は一気に逼迫すると考察するレポートも存在14します。特に、国際的にも評価の高い手法で創出された「質の高い」クレジットの獲得競争はレピュテーションリスクを低減することに加え対象地域への貢献等を主張することでブランディング戦略においても有益であることから調達に向けた競争が激化することが予想されます。
もちろん、各社の省エネ努力が想定以上に進展した場合や、政府による価格安定措置が機能した場合は、カーボン・クレジットの需給逼迫がある程度緩和されるシナリオも考えられます。しかし、企業の中長期戦略の検討においては、クレジットの需要が供給を上回り高騰する自社にとってシビアなシナリオを前提に、安定的な調達先を早期に確保する視点が必要となります。
脚注
12 BloombergNEF(2024), " Carbon Credits Face Biggest Test Yet, Could Reach $238/Ton in 2050, According to BloombergNEF Report "
13 経済産業省HP,「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」,P21
14 ERM HP,「GX-ETS の本格稼働に伴うJCM クレジット需要の高まり」
3. 民間での取組事例
カーボン・クレジットへの関与は、企業ごとにその戦略や目的が多様化しています。従来多かったブランディング目的でのボランタリークレジット活用に加え、GX-ETSの始動を契機に規制対応のための活用や自社の強みを活かした新規事業としてのプロジェクト投資等新たな動きが加速しつつあります。本章では、カーボン・クレジット領域において自社の強みを活かした先進的な戦略を実践する企業の事例の一部を紹介します。
(1)事例1:東京ガス ー 購入から開発、国際ルール形成まで手がける段階的戦略
エネルギー供給事業者として大規模な排出削減が求められる東京ガスは、クレジットの「購入者」として市場への理解を深め、段階的に「開発者」へと移行し、さらには市場の「ルール形成」にも関与するという戦略的なアプローチを実践しています15。
段階1(購入者・学習者): 同社はまず、天然ガスの採掘から燃焼までのGHG排出量をクレジットで相殺した「カーボンニュートラルLNG(CNL)」の調達・販売から着手しました16。これにより、顧客の脱炭素ニーズに応えつつ、世界の主要なクレジット事業者とのネットワークを構築し、取引実務や品質評価に関する知見を内部に蓄積することが可能になったと考えられます。
段階2(開発者・供給者): 次に、その知見を活かし、信頼性の高い自然由来のクレジットを創出する海外の「ネイチャー・ベースド・カーボンファンド」へ最大2,500万米ドルの出資を決定しました17 。これにより、高品質なカーボン・クレジットの長期安定確保を目指しています。
同社は、植生中に炭素を固定・吸収する植林等によるカーボン・クレジットは、中長期的に調達が難しくなると予想し、同ファンドに最大2,500万米ドルの出資を行うことで、信頼性の高い自然系カーボン・クレジットを2037年までの12年間にわたり相当規模調達することを目指しています。これは、高品質かつ生産費用の低いカーボン・クレジット創出の適地から権益が確保されるカーボン・クレジットの創出ビジネスの本質を見据え、購入者の立場から、クレジット創出プロジェクトを支える出資者側へと歩みを進める戦略的打ち手であると考えられます。
段階3(ルール形成への関与): さらに同社は、クレジットの品質を担保する上で重要な「人権への配慮」に着目しています。現行の国際ガイドラインでは評価項目が不明確であるという課題に対し、東京海上日動火災保険、日本工営等と共同で、クレジット創出者が満たすべき人権配慮の評価項目や管理体制を明記した「人権尊重のためのフレームワーク」を2025年に策定・公表18、同9月には関西電力他と共同でガーナの植林プロジェクトへの参画、同プロジェクトで同フレームワークを活用する旨を公表しました19。
これは、黎明期の市場において自社の調達基準を高度化するだけでなく、市場全体の信頼性向上に貢献することで、グローバルルール形成におけるプレゼンス拡大も可能とすることを示す事例であると考えられます。
(2)事例2:NTTグループ ― 地域内での炭素循環モデル創出と自社利用
NTTグループは、自社のカーボンニュートラル達成という大きな経営課題に対し、J-クレジットの「創出支援」と「自社利用」の両面から取り組むプロシューマー戦略を推進しています。
創出支援(「森かち」による地域循環モデル): グループ傘下のNTTコミュニケーションズ(発表当時の企業名。現在はNTTドコモビジネス)は、住友林業と共同で、日本の森林資源を活かしたJ-クレジット創出と地産地消を支援するプラットフォーム「森かち」を展開しています20。これは、森林所有者へのクレジット認証取得支援と、創出されたクレジットの地域企業や自治体へ販売・活用までを一体でサポートするサービスです。クレジットの売却益が地域の森林保全活動に還元される「炭素と資金の地域内循環モデル」を構築し、国内のクレジット供給量拡大に貢献しています。
自社利用(事業活動におけるカーボン・オフセットの実践): NTTグループは、クレジット創出を支援するだけでなく、自らもJ-クレジットの積極的な利用を進めています。NTT Sports XとNTTドコモビジネスは、NTT Sports Xが運営するラグビークラブ「浦安D-Rocks」のJAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25シーズンにおけるホストゲーム全9試合において、試合開催に伴い発生するCO2をオフセットする「カーボン・オフセット試合」の取り組みを実施21しています。また、NTT西日本では、自社の創出支援を手掛けた森林吸収系のJ-クレジットの一部(400t-CO2)を購入し、自社の2023年度の温室効果ガス排出量のうちScope1排出量の一部をカーボン・オフセット22しています。
このように、同社グループは、クレジットの創出支援を通じて市場への供給を支えつつ、自らも需要家としてその市場に参加することで、自社のカーボンニュートラル推進と国内クレジット市場の活性化を両輪で進めています。
脚注
15 東京ガス HP,「カーボンオフセットに関する取り組み」
16 東京ガス HP,「シェル・イースタン・トレーディング社からのカーボンニュートラルLNGの購入について」
17 東京ガス HP,「信頼性の高い自然系カーボンクレジット創出を目的とする「ネイチャー・ベースド・カーボンファンド」への最大2,500万米ドルの出資について」
18 東京ガス HP,「東京海上グループと連携、カーボンクレジットの信頼性向上を目的とした「人権尊重のためのフレームワーク」を策定」
19 東京ガス HP,「ガーナにおけるカーボンクレジット創出プロジェクトへの参画について ~関西電力、3Tとの協業による信頼性の高いカーボン・クレジットの創出~」
20 NTTコミュニケーションズHP,「日本初、GISで森林由来J-クレジットの創出者・審査機関・購入者の3者を支援する『森林価値創造プラットフォーム』を提供開始」
21 浦安D-Rocks HP,「2024-25シーズンのラグビーホストゲーム 全9試合でカーボン・オフセット達成へ! NTTドコモビジネスが提供するカーボンクレジットを活用」
22 NTT西日本HP,「地域創生事業で創出されたカーボン・クレジットを活用 NTT西日本グループの脱炭素経営を加速」
4. リスクの類型と管理アプローチ
カーボン・クレジットの活用は、前述の議論のとおり企業に対し多くの機会を提供する一方で、複合的かつ複数のリスクを内包しています。以下、カーボン・クレジットに関わるリスクの主要項目について記載します。
(1)品質・物理的・信用リスク
まず、クレジットそのものの品質に関わるリスクが存在します。クレジットの本質的価値は、その創出プロジェクトがなければ実現しなかった削減・吸収量であること(追加性)と、その効果が永続的であること(永続性)等により担保されます。しかし、ICVCMによるCCPsの公表23等近年の品質に関するルールメイク進展で減少はしたものの、プロジェクトの前提となるベースラインの評価が甘く、実態以上の効果を謳う「質の低い」プロジェクトが存在すると一部メディアで指摘されています24。
また、森林火災や風水害等によってプロジェクトそのものが毀損する物理的リスクや、デベロッパーの能力不足により当初予定した量のクレジットが発行されない発行遅延や信用リスクも存在します。
(2)途上国におけるレピュテーション・人権リスク
慎重な対応が求められるリスクの一つとして、レピュテーションや人権に関わるリスクが挙げられます。自然由来のプロジェクトの多くは途上国で実施されていますが、プロジェクトの計画が甘く本来のGHG吸収量以上のカーボン・クレジットを発行してしまうことで、(1)同様、品質に対し疑義が生じ、カーボン・クレジットの活用者がグリーンウォッシュ批判に晒されるレピュテーションリスクが存在します。
また、プロジェクトにおける人権侵害の疑惑も報道されており、例えば、ケニアのカシガウ回廊REDD+プロジェクトでは組織的な性的虐待の疑惑25が報じられ、その価値が大きく損なわれる事態となりました。このようなプロジェクトのクレジットを調達・使用した場合、企業は人権侵害に加担したと見なされるレピュテーションリスクに直面することとなります。
(3)リスク管理のアプローチ
これらのリスクは、黎明期の市場であるがゆえに、リスクの全貌がいまだ明らかになっていない点も相まって従来の金融的な手法のみでヘッジすることは困難です。
それゆえ、まずは小規模なクレジット調達を通じて、方法論や市場関係者への理解を深める「スモールスタート」に早急に着手し、知見蓄積を図りながらステップバイステップで歩みを進めることが重要であると考えられます。一方で、優良なプロジェクトやパートナーを巡る競争が激化しつつある現在、残された時間的猶予は決して長くはありません。「為さざるリスクが、為すことによるリスクを大きく上回る」局面においては、早期に検討に着手し、スモールスタートであっても、検討の歩みを早める意識が重要となります。
サプライチェーン全体のリスク分析には多大な労力を要するため、全て自社で検討を内製化する必要はありません。本分野で先行する企業との連携や、関連するコンソーシアムへ参加することも情報収集の観点で有益となり得ます。
脚注
23 The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM)はカーボン・クレジットの品質の担保を目指す独立の非営利団体である。同団体は高品質のカーボン・クレジットが具備すべき要件について規定したThe Core Carbon Principles (CCPs)を公表しました。有力な基準として業界で広く認識され、準拠したカーボン・クレジット創出プロジェクトの数量は増加しています。CCPsの詳細については以下をご参照ください。
ICVCM HP,” The Core Carbon Principles”
24 代表的な報道として、The Guardian(2023)” Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows” が挙げられます。同報道後に大手認証機関が同誌に対する反論を掲載したほか、同誌が根拠とする論文の正確性については様々な見解が見られます。
25 SOMO(2023),” Offsetting human rights Sexual abuse and harassment at the Kasigau Corridor REDD+ Project in Kenya”
5. 結論
GX-ETSにおける排出量取引への参加義務化は、企業経営における炭素の価値の戦略的位置付けを大きく変化させる可能性があります。これまで一部の先進企業のものであったカーボン・クレジットの活用は、今や多くの企業にとって自社の排出削減努力と並行して検討すべき、重要な戦略的選択肢となりつつあります。
しかし本稿で見てきたように、カーボン・クレジットに関しては品質疑義や、プロジェクト対象の物理的被害、人権、価格変動等多様なリスクが存在します。将来の市場拡大や排出強化局面で必要に迫られてから拙速に対応すれば、クレジットの高値掴みや低品質でハイリスクなプロジェクトへの投資といった手痛い失敗を招きかねません。その点において、現在最も回避すべきリスクは、GX-ETSやカーボン・クレジット市場拡大による潜在的な機会やリスクシナリオを把握しないまま、受け身で規制強化の潮流を迎えてしまうことです。
今後の炭素価格の動向次第では、カーボン・クレジットは次世代の「戦略物資」となる可能性を秘めています。その時、十分な知見やネットワーク、調達能力を持つか否かは、企業の競争力を大きく左右し得ます。その点においてスモールスタートであっても早急にR&Dのための具体的な行動を起こすことが重要であると言えます。
以上、本稿においては、GX-ETSが企業経営に与える影響とカーボン・クレジットの戦略的な位置付け、先進企業における活用事例と活用時に留意すべきリスクについて概観しました。黎明期の市場であることと、何より筆者の不徳により不正確の誹りは免れないものの、拙稿がお目通しいただいた読者の戦略策定の一助となれば望外の喜びです。
執筆者プロフィール
柴田 智文
東京海上日動火災保険株式会社 マーケット戦略部GX室
2011年にエネルギー企業入社後、主に経営企画部門において 政策対応と経営戦略・計画策定業務に従事。2017年~2020 年、一般財団法人日本エネルギー経済研究所に出向、政府機関・法人顧客に対する欧米を中心としたエネルギー政策の調査・研究に従事。2022年東京海上日動火災保険(株)入社。GX分野の商品戦略立案・開発業務に従事。
PDFファイルダウンロード
東京海上dR GXレポート「カーボン・クレジットが産業界へ与える影響 ~シリーズ③「GX-ETS義務化による企業経営への影響とカーボン・クレジット戦略へのインプリケーション」~」PDF
