東京海上dR GXレポート「国内外の原子力政策・産業に関する最新動向」
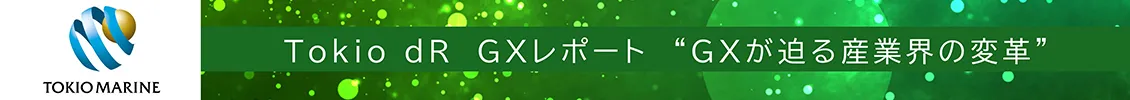
2025/10/7
目次
- 原子力をめぐる情勢
- 各国の動向
- SMRの開発動向
- 今後の課題
東京海上dR GXレポート「国内外の原子力政策・産業に関する最新動向」PDF
(一財)日本エネルギー経済研究所 資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット
主任研究員 下郡 けい
協力:東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー
脱稿日:2025年10月6日
近年、世界的なエネルギー情勢の変化の中で、原子力発電に対する注目が高まっています。国際原子力機関(IAEA)によると、2025年8月現在、世界31か国が原子力発電所を導入しており、合計で439基(約396GW)の原子炉が運転しています(うち23基・約20GWは運転中断中)。国別にみると、米国の94基(約97GW)、フランスの57基(約63GW)、中国の57基(約55GW)の3か国で世界の原子力発電設備容量の54%を占めていますが、既設炉の多くは先進国に集中しています。なお、発電電力量でみると、原子力発電は世界の発電電力量の約10%をまかなっています。日本では、33基(約32GW)の原子炉のうち、14基(約13GW)が福島第一原子力発電所事故後に策定された新規制基準の適合審査に合格し、営業運転を再開しました。
世界初の原子力発電は1951年に米国で開始され、1973年の石油危機を経て、各国で原子力発電の開発が進められました。しかし、1979年のスリーマイル島原子力発電所事故(米国)、1986年のチョルノービリ原子力発電所事故(旧ソ連、現ウクライナ)の発生を受け、世界の原子力利用は停滞します。2000年以降、原油価格の高騰と温室効果ガス排出削減への関心の高まりから、先進国や新興国(中国やインド)で新規建設が進められました。その後、2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて、改めて脱原子力の方針を示した国や、引き続き原子力を利用する国など、各国の立場はそれぞれのエネルギー需給をめぐる状況などを踏まえて異なっていました。
本稿では、エネルギー安全保障、気候変動対策、将来の電力需要の拡大の観点から、特にロシアによるウクライナ侵略が起きた2022年以降の国内外における原子力政策、産業動向について概説します。
1. 原子力をめぐる情勢
(1)エネルギー安全保障の観点
2022年2月のロシアによるウクライナ侵略は、世界のエネルギー情勢に大きな影響を与えました。例えば、欧米や日本によるロシアへの経済制裁措置によるエネルギー取引への制約や、ロシアによる報復的な措置としてのエネルギー輸出削減や停止を引き起こしています。これによる化石燃料価格の高騰や供給源確保の競争激化は、エネルギーの安定供給や安全保障の確保を各国政府が重要課題として位置付ける契機となりました。エネルギー安全保障に対する各国の注目が高まる中で、安定的なエネルギー供給を期待できる原子力発電への関心も高まってきています。原子力発電の特徴の一つとして、燃料となるウランは、ロシア以外にも政情の安定した国々に分布しており、通常は長期契約で売買されるため価格変動リスクが低くなっています。また、ウラン燃料は一度原子炉に装荷されると4~5年程度使用することができ、原子炉は一度運転開始すると1年以上継続して運転することが可能です。そのため、原子力発電は日本では準国産エネルギーとして位置づけられています。このような特徴から、特にロシア産化石燃料にエネルギー供給の多くを依存していた欧州各国は、原子力既導入国では既設原子炉の運転延長や新規建設、新規導入国では具体的な新設計画に向けた動きの加速がみられるようになりました。
なお、ロシアは世界のウラン濃縮能力の40%を占めています。ロシア製原子炉が稼働する欧州各国(ブルガリアやチェコ、フィンランド、スロバキア)では、燃料供給契約をWestinghouse社(米国)やFramatome社(フランス)といった新たなサプライヤーと締結するといった燃料供給先の多様化の取り組みも進められています。2023年4月には、米国、英国、フランス、カナダ、日本の5か国が、国際原子力市場からロシアを排除することを目的とした同盟(核燃料同盟)を発表し、同月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケや翌月のG7広島首脳コミュニケでも、核燃料を含む原子力サプライチェーンの構築にコミットすることが掲げられました。
(2)気候変動対策の観点
2023年12月、アラブ首長国連邦で開催された第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)の成果文書(UAEコンセンサス)では、炭素排出量を削減するための重要なアプローチの一つとして「原子力」が初めて明記されました。また、COP28期間中には、「2050年までのネットゼロ達成に向けて、世界の原子力発電設備容量を2020年比で3倍に増加させる」という誓約が署名されました。COP28では25か国、翌年のCOP29では新たに6か国が署名し、世界31か国が参加しています。なお、すべての原子力導入国が誓約に署名したわけではなく、例えば中国やロシア、インドなどは署名していません。その一方で、原子力発電所を建設中の国(トルコ)や導入を検討している国(例えばポーランドやカザフスタン、ケニアなど)が誓約に署名しています。
同誓約では、世界銀行や国際開発金融機関、地域開発銀行に対して、必要に応じて原子力を各機関の融資対象に含めることを奨励していました。2025年6月、世界銀行は原子力発電プロジェクトへの融資を禁止する措置を解除し、既存原子炉の寿命延長及び新規建設プロジェクトへの資金提供を開始することを決定しました。同行による原子力発電所への資金提供は1959年が最後(イタリア初の原子力発電所建設への融資)であり、2013年から同行の専門分野外として原子力発電への融資を行ってきませんでした。この世界銀行の方針転換は、他の国際金融機関や投資家が原子力に係る融資を前向きに検討する道を開くものと言えます。同月には、世界銀行とIAEAが、原子力協力に向けたパートナーシップを正式に締結しました。
(3)電力需要の観点
国際エネルギー機関(IEA)が2025年4月に発表した「Energy and AI」によると、2024年の世界の電力需要の約1.5%(415TWh)がデータセンターによるもので、米国(45%)が最大の割合を占め、中国(25%)、欧州(15%)と続きます。2017年以降、データセンターの電力需要は年間約12%のペースで急速に拡大しており、2030年までに約945TWhと2024年比で倍増すると見込まれています。さらに、2030年以降は不確実性が高いものの、IEAの分析では、2035年までに世界のデータセンター電力需要が約1200TWhに達するとの見通しが示されています。
日本においても、将来の電力需要の伸びが見込まれています。電力広域的運営推進機関(OCCTO)が2025年1月に発表した今後10年間の電力需要の見通しでは、データセンターや半導体工場の新増設などによる電力需要の増加によって、2034年度における全国の電力需要は852.4TWhと2024年度比で約6%の増加と予測されました。
原子力発電は、ベースロード電源として安定的な電力供給が可能という特徴があります。後述するように、特に米国では、大手テック企業を中心に原子力発電所からの電力供給の確保や、小型モジュール炉(SMR)などの開発企業との提携が見られます。2025年3月には、Amazon社、Dow社、Google社、Meta社などの大手14社が「大規模エネルギー使用者誓約(Large Energy Users Pledge)」に署名し、前述の原子力発電設備容量を2050年までに3倍にするという目標を支持すると発表しました。
2. 各国の動向
(1)米国
米国では、閉鎖した原子炉の再稼働に向けた動きが進んでいます。2023年10月、Holtec社がパリセード原子力発電所(ミシガン州、805MW、2022年5月閉鎖)の再稼働の意思を発表したことを皮切りに、Constellation社がスリーマイル島原子力発電所1号機(ペンシルベニア州、819MW、2019年9月閉鎖1 )を再稼働のうえMicrosoft社へ20年間の電力供給を行う計画を発表、またデュアン・アーノルド原子力発電所(アイオア州、601MW、2020年8月閉鎖)も再稼働に向けた動きが進んでいます。大手IT企業による他の例として、Amazon子会社のAWSによる、サスケハナ原子力発電所(ペンシルベニア州、1.257GW)に隣接して直接電力供給を受けるキュムラスデータセンターの買収が挙げられます。サスケハナ原子力発電所からAWSへの電力供給については、系統サービスに関するコスト負担を不当に回避する可能性などが問題視され、連邦エネルギー規制委員会(FERC)が供給契約の拡大を認めない判断を下しました。このような、電源から直接電力供給を受ける「共立地負荷(co-located load)」の扱いが注目されました。共立地負荷は、系統接続のリードタイムの短縮や送電効率の向上、系統の空き容量の増加というメリットもあるものの、米国ではルールの策定が十分に追いついていないのが現状です。その後、サスケハナを所有するTalen Energy社は当初目指していた契約形態を変更し、電力系統への供給を介する形でAWSへの供給契約を締結しました。日本でもデータセンターの立地が進みつつある中で、既存の系統接続のルールなどが十分に明確か、米国と類似の問題が日本でも起こり得るのかといった点について、米国の連邦及び州レベルでの検討を踏まえつつ、今後の課題を洗い出すことが求められます。
また、大手IT企業はSMRなどへの投資も積極的に進めています。例えば、Amazon社は、X-energy社製の高温ガス炉型SMRの商業化に向けて約5億ドルの出資を発表し、米国で2039年までに5GW以上を稼働させることを目指しています。さらにAmazon社は同じ日に、ワシントン州におけるEnergy Northwest社とのSMR開発(4基)、バージニア州に立地するノースアナ原子力発電所付近で少なくとも300MWのSMR開発を検討する合意に調印しました。Google社は、Kairos Power社が開発するフッ化物塩冷却高温炉(KP-FHR2 )を2035年までに最大で500MW導入し、データセンターに電力を供給する電力購入契約を締結しています。
(2)フランス
マクロン大統領は、2022年2月にEPR2(改良型欧州加圧水型炉)を少なくとも6基、さらに追加で最大8基新設することを発表しました。これは、送電系統運用者RTEが2021年10月に発表した、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた6つの電源構成シナリオを比較した報告書(Futurs Energétiques 2050)の内容を踏まえて公表されたものです。同報告書では、カーボンニュートラルの実現には再生可能エネルギーの大幅な導入が欠かせないとする一方、電力の安定供給を確保しつつ、より安いコストで確実に目標を達成するためには、EPR2の新設が必要になるとの見解を示していました。EPR2の新設サイトとして、既設炉が立地する3地点が選定され、そのうちの1地点では2023年6月に認可プロセスが開始されました。既設炉が立地する地域での新規建設に要する期間を短縮するため、2023年6月に「既存原子力サイト近傍における新規建設及び既存炉の運転継続に係る手続の迅速化に関する法」が公布されています。また、2025年3月に開催された、閣僚級会合の「原子力政策評議会」では、EPR2新設の資金調達などが議論され、建設費用の少なくとも半分を国が優遇融資で支援し、最大€100/MWhの差額決済取引3 を実施することが合意されました。なお、フランスの原子力発電所を所有・運転するEDF(フランス電力)は、2023年6月にフランス政府が株式及び議決権を100%取得し、完全国有化しています。
(3)イギリス
2022年4月に「エネルギー安全保障戦略」が発表され、2050年までに最大24GWの原子力発電設備容量を導入し、電力供給の25%を原子力でまかなうという目標が設定されました。その後、2024年7月の総選挙で労働党が地滑り的勝利を収めて政権が交代しましたが、労働党政権においても、2030年までにクリーン電力化を達成する(少なくとも95%を低炭素電源とする)という目標の下、既設炉の運転期間延長、建設中のヒンクリーポイントC原子力発電所の運転開始、計画中のサイズウェルC原子力発電所やSMRなどの新設に取り組むことが掲げられています。
大型炉の新規建設に関連して、2022年4月に「原子力エネルギー(資金調達)法」が成立し、規制資産ベースモデル(RABモデル)を利用して国内の将来の原子力発電所の資金調達を行うことが盛り込まれました。RABモデルは、規制当局が認可した投資の回収を、利用者(需要家)が支払う規制料金を通じて、建設中、試運転中、運転中の各段階で行う仕組みです。2025年7月、イギリス政府が株式の44.9%を保有するサイズウェルC原子力発電所の建設計画が最終投資決定に至りました。同計画にはRABモデルが適用され、2基のEPRが建設される予定です。また、イギリス政府はサイズウェルCに続く大型炉の建設候補地として、ウィルファを2024年5月に選定しました。同サイトは、2024年3月に日立製作所からGreat British Nuclear(現在はGreat British Energy – Nuclear、以下GBE-N)4 が買収した敷地です。
SMRに関連しては、GBE-Nが、国内のSMR技術を選定する競争プロセス(SMRコンペティション)を2年間にわたって実施し、2025年6月にRolls-Royce社製のRolls-Royce SMRがイギリスで初めて建設されるSMR炉型に選定されました。GBE-Nは2025年中にサイトを選定し、2030年半ばまでにSMRプロジェクトを送電網に接続することを目指しています。
(4)他の欧州諸国
ベルギーは、2003年に策定された「脱原子力法」で原子炉の運転期間を40年に制限し、既設炉を順次廃止する予定としていましたが、ロシアのウクライナ侵略を踏まえ、2基の運転期間延長(2025年から10年間)を決定しました。さらに、2025年2月に発足した中道右派が主導する5党連立政権は、エネルギー供給強化の重要性から、原子力発電の段階的廃止政策の撤廃を表明しました。同年5月には連邦議会が原子力発電の段階的廃止を撤回し、新規建設を認める法案を、賛成多数で可決しています。
スウェーデンでは、2022年10月に発足した連立政権の合意において、既存サイト以外での原子炉の新設を禁止する規定及び運転中の原子炉数を10基までに制限する規定を撤廃する方針を示し、議会の承認を得ました5。2023年11月には、2035年までに大型炉2基分、2045年までに最大10基分を目指すロードマップを政府が発表しています。さらに、新規建設を検討する企業への国家補助に関する政府法案が2025年5月に議会で可決され、新設に向けた環境整備が進められています。
ドイツは、福島第一原子力発電所事故後、脱原子力政策をとりました。2022年末までに既設炉を段階的に閉鎖する予定でしたが、2022年・23年冬季に電力系統が危機的状況に陥る可能性を完全には排除できないとして、2022年末に停止予定であった既設炉3基を2023年4月まで運転継続することが決定されました。これら3基は2023年4月に閉鎖され、ドイツは脱原子力を完了しています。2025年5月に発足したCDU/CSUとSPDの連立政権は、閉鎖した原子力発電所の再稼働や回帰を否定しています。しかし同時に、EUレベルでの新たな原子力技術(SMRなどを念頭に置く)の支援には反対しない姿勢を示しています。
(5)中国・ロシア
2025年8月現在、世界15か国で62基の原子炉が建設中の段階にありますが、中国製及びロシア製原子炉の割合はそれぞれ42%ずつと高い割合を占めています。中国は主として国内で自国製原子炉の新規建設を着実に進めており、ロシアは国内に加えて積極的に海外での新規建設を行っています(バングラデシュやエジプト、インド、トルコなど)。両国ともに国営の原子力企業が政府と一丸となって国内外の原子力発電開発を進めています。特にロシアの輸出プロジェクトでは、国営原子力企業ロスアトムが建設・運転・燃料供給などを一貫したサービスとして提供しているとともに、原子力の新規導入国への人材育成サービスにも積極的に取り組んでいます。
また、中国やロシアは、第4世代炉6やSMRの開発にも積極的で、実機の導入も進めつつあります。SMRについて、例えば中国は、軽水炉型SMRの玲龍一号(ACP100)の実証炉を2021年7月に着工し、2026年までに2基の運転開始を目指しています。また、ペブルベッド型モジュール式高温ガス炉(HTR-PM)の実証炉2基が2021年12月に送電を開始し、2023年12月から営業運転を開始しました。ロシアは、洋上浮体式原子炉を開発しており、極東のペヴェクで2020年5月から営業運転を開始しました。新たな浮体式原子炉(RITM-200S、2基)や、陸上設置型SMR(RITM-200N)、鉛冷却高速炉(Brest-OD-300)の建設も進んでいます。
(6)日本
日本においても、ウクライナ侵略後のエネルギー価格高騰と脱炭素化に向けた取り組みを踏まえて、原子力発電の利用に関する議論が活発化しました。2023年5月には、原子炉の運転期間見直しを含む「GX脱炭素電源法」が成立し、原子力発電所の運転期間に関する新たな措置が認められました。これは、原子力規制委員会による新規制基準適合審査や、運転差し止めなどを求める訴訟によって原子炉が停止していた期間を、原子炉の運転期間(最長60年)から差し引くというものです。ただし、原子炉の高経年化の技術評価を運転開始から30年、その後は10年ごとに行い、その都度運転継続の可否を判断することとなりました。
既設炉の再稼働については、2025年8月時点で14基が営業運転を再開しています。PWR(加圧水型原子炉)の再稼働が先行していましたが、2024年末から2025年初めにかけてBWR(沸騰水型原子炉)として女川2号機、島根2号機が再稼働しました。2024年の発電電力量に占める原子力発電の割合は、9.6%となっています。
2025年2月に策定された「第7次エネルギー基本計画」では、原子力発電に関する記述が2011年以降の基本計画から大きく変化しました。第7次計画では、再生可能エネルギーや原子力などの脱炭素電源を最大限活用することが不可欠とし、2011年以降の計画では想定されていなかった新増設・リプレースについても、GX基本方針(2023年2月閣議決定)で明記された「廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への立て替え」を具体的に進めていくことが盛り込まれました。「2040年度におけるエネルギー需給の見通し」では、発電電力量が2040年度に1.1~1.2兆kWh程度と増加に転じると見込まれる中、原子力発電が2割程度をまかなうとされています。これは、原子力発電による発電電力量の増加(2040年度には2022年度実績の約4倍)を示唆しており、日本において既設炉の安定的な稼働や追加的な再稼働、新規建設の進展が一層求められます。
脚注
1 1979年の事故は2号機で発生し、同炉は閉鎖。
2 フッ化物塩冷却高温炉は、電気出力14万kW、燃料に固体セラミック燃料、冷却材に溶融塩(低圧の液体フッ化物塩)を用いるもの。電力と高温の熱を供給する。
3 差額決済取引(Contract for Difference)は、投資回収に必要な長期的な「基準価格」を設定し、指標となる市場の価格である「指標価格」との差額を発電電力量に応じて発電事業者と買取主体の間で精算する方法。
4 Great British Nuclearは、原子力発電プロジェクトの設計、建設、運転を促進するため、エネルギー法2023に基づいて設立された独立機関。選定された技術の開発段階において共同資金を提供し、適切な資金調達とサイト配置を確保する。最初の優先事項としてSMR技術の選定プロセスを実施。2025年6月にGreat British Energy – Nuclearへ名称変更。
5 Riksdag, “Yes to the Government’s spring amending budget”, 20 June 2023; Riksdag, “New nuclear power in Sweden”, 29 November 2023.
6 燃料の効率的利用、放射性廃棄物の最小化、核拡散抵抗性(核物質やそれに関連する施設が軍事目的に転用されることを防止あるいは阻止する能力)の確保といったエネルギー源としての持続可能性、炉心損傷頻度の飛躍的低減や敷地外の緊急時対応の必要性排除など安全性/信頼性の向上、及び他のエネルギー源とも競合できる高い経済性の達成を目標とする次世代原子炉概念。2001年7月に結成された第4世代国際フォーラムにおいて、2030年までの実用化を目指す概念が6つ選定された(ガス冷却高速炉、鉛冷却高速炉、溶融塩炉、超臨界水冷却炉、ナトリウム冷却高速炉、超高温原子炉)。(ATOMICA, 「第4世代原子炉の概念」)
3. SMRの開発動向
原子力発電に関連して、これまで第4世代炉やSMRの技術開発が長らく進められてきました。特に近年、SMRに対する注目が高まっており、前節でも紹介した通り、各国でSMRの開発・導入検討が進められています。SMRは、1基あたりの電気出力が300MW以下という小さな原子炉を指します。一つでも複数でも配備が可能であるためエネルギー需要や送電網の規模が小さい地域や遠隔地に導入できること、工場で製造された機器などをモジュール化して現地で据え付けることによる工期の短縮、電力以外にも熱供給や水素製造といった産業分野での利用を含む他用途での利用、などが期待されています。
経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)の分析7では、世界で127の炉型を特定し、74の炉型について分析しています。このうち7つの炉型は建設中または運転中の段階にあり、51の炉型が事前許認可または許認可プロセスの段階にあるとされ、技術的な成熟度にばらつきはあるものの多様な設計が存在しています。資金調達の面では、2024年版のOECD/NEA分析以降、SMR設計の資金調達発表が81%増加しているとされ、SMRのサプライチェーン開発と初期段階の製造能力の進展が促進されていると言えます。

図 SMRの立地候補地の表明数(国別、サイト所有者タイプ別)
(出所)NEA (2025), p. 17
上図が示すとおり、SMRプロジェクトの立地候補地の多くは政府機関や公益事業者、国立研究所が所有するサイトとなっていますが、民間企業が所有するサイトも増加しつつあります。産業や商業といった需要地付近や、廃止予定の石炭火力発電所サイトにおける導入が検討されているところです。ビジネスモデルとしても、電力会社のみを所有者・運営者とする形態ではなく、建設・所有・運転(BOO)モデルや電力購入契約(PPA)といった多様な形態が検討されています。
多くのSMRの炉型は、ウラン235の濃縮度を5-20%まで高めた高純度低濃縮ウラン(HALEU)を燃料として利用する計画ですが、NEAによるとHALEUの供給契約を締結したSMR炉型は2つのみであり、HALEUの供給確保が課題の一つとして挙げられます。また、従来の原子炉では酸化ウランセラミック燃料が一般的でしたが、SMRの炉型の中には現在商業規模の製造施設がない新型燃料(TRISO燃料や金属燃料、熔融塩燃料など)を用いるものもあり、燃料製造のインフラ整備が必要とされます。
脚注
7 NEA (2025), The NEA Small Modular Reactor Dashboard: Third Edition, OECD Publishing, Paris.
4. 今後の課題
前述のように、エネルギー安全保障や脱炭素化への取り組みの中で、原子力発電が果たす役割に対する関心や期待が高まってきました。ただし、原子力発電は課題も抱えています。各国に共通する原子力発電の課題の一つとして、大規模な初期費用や長いリードタイムを要するという原子力発電の特徴が挙げられます。近年、先進国における建設計画では大幅な遅延が発生し、天然ガス火力発電や再生可能エネルギー発電といった他の発電技術との競争の中で、原子力発電は依然として厳しい状況に置かれています。新規建設の観点では、初期投資と長期のリードタイムという事業者が負うリスクを低減するような制度(一つの例としてイギリスのRABモデル)の導入検討は、原子力発電事業の予見可能性を高め、具体的な新規投資を呼び込みやすいと考えられます。また、先進国の建設遅延の例(米国のボーグル3・4号機、フランスのフラマンビル3号機、フィンランドのオルキルオト3号機)から得られる教訓を今後のプロジェクトに十分に反映することも重要です。
日本では、電源投資の予見可能性の向上、脱炭素電源への新規投資の促進を目的として、長期脱炭素電源オークションが2024年1月から開始されました。原子力発電については、1回目のオークション(2024年4月結果公表)では新設・リプレースを対象として島根3号機が、2回目のオークション(2025年4月に結果公表)では既設原子力発電所の安全対策投資も対象として追加され、3基(泊発電所3号機、柏崎刈羽原子力発電所6号機、東海第二発電所)が約定しました。対象が拡大されたことで、発電事業者の安全対策投資の回収予見性が高まると期待されます。同時に、資材費の高騰や金利上昇、バックフィット(新たな規制への事後的な対応)などによる追加費用といったリスクへの対応や、建設期間中に先行して発生する費用の確保など、制度の改善も求められるところです。なお、原子力損害の賠償責任について、日本では事業者が無限責任を負う一方、例えば米国や英国、フランスでは事業者の損害賠償措置額に上限が設けられています。投資の予見可能性を高めるうえで、原子力損害賠償制度の設計も注目されます。
日本における既設炉の再稼働の観点では、新規制基準適合審査を合理的・効率的に進めることが求められます。既設炉の再稼働が徐々に進んでいるものの、依然として設置変更許可をめぐる審査中の炉も数少なくありません。稼働していない炉の停止期間は平均で14年強となり、これまでの審査で得られた知見を活用しながら、原子力規制委員会と事業者による適切なコミュニケーションの下で審査が進められることが重要です。
エネルギー安全保障の観点では、燃料のサプライチェーンの多様化(特にロシア依存の低減)の実現が、SMR向けの燃料製造の商業化も含め、肝要となります。先進国における濃縮や燃料製造は民間企業が担っており、能力拡張の新規投資には将来の燃料需要が十分に見込めることが不可欠です。長期的な視座に基づく政策や制度を踏まえた、原子力発電所の具体的なプロジェクトの動向が、引き続き注目されます。
執筆者プロフィール
下郡 けい
(一財)日本エネルギー経済研究所 資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット 主任研究員
