東京海上dR GXレポート「トランプ第二次政権の政策運営とGXへの影響」
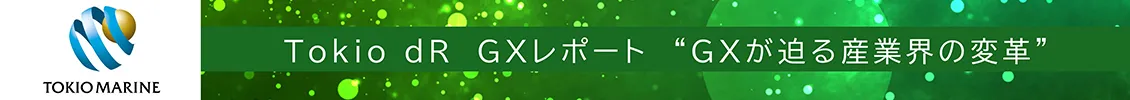
2025/4/2
目次
- 「エネルギードミナンス」の追求
- 化石燃料の増産・輸出拡大
- 環境規制の緩和
- IRA(インフレ削減法)の見直し
- 再生可能エネルギー・原子力
東京海上dR GXレポート「トランプ第二次政権の政策運営とGXへの影響」PDF
(一財)日本エネルギー経済研究所 資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット
主任研究員 下郡 けい
協力:東京海上dR「GXの産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー
脱稿日:2025年3月25日
米国では、2024年11月の大統領選挙で共和党のトランプ氏が勝利し、同日に実施された連邦議会選挙でも上下両院で共和党が多数派を占め、いわゆる「トリプルレッド」となりました。共和党が上下両院を押さえることで、大統領の掲げる政策を実現しやすくなると考えられます。
バイデン政権は、脱炭素化に向けた取り組みを主導しました。対外的にはパリ協定へ復帰、国が決定する貢献(NDC)を策定、液化天然ガス(LNG)輸出許可を一時停止し、国内的には環境規制を強化、インフレ削減法(IRA)を成立させました。トランプ第二次政権では、就任初日から多くの大統領令が署名され、パリ協定からの 再離脱の表明や、国家エネルギー緊急事態の宣言、米国のエネルギーの解放と題しエネルギー資源開発にとっての制約の特定とその撤廃などが発表され、政策を大きく方向転換しています。
2026年に実施される中間選挙では下院で民主党が議席を伸ばし多数派となる可能性もありますが、トランプ大統領が向かい風なく政策を推し進められる期間にどのような変化が生じ得るのか、トランプ第二次政権のエネルギー関連政策で注目される5点について概説します。
1. 「エネルギードミナンス」の追求
トランプ政権のエネルギー関連政策において重要となる概念に、「エネルギードミナンス」があります。エネルギードミナンスはトランプ第一次政権(2017~2021年)で打ち出された概念で、ドミナンスとは支配や優勢という意味です。トランプ第二次政権は、第一次政権に続いて「エネルギードミナンス」を追求すると表明しており、「米国のエネルギードミナンスによってインフレを抑え、中国(やその他)とのAI競争に勝利し、米国の外交力を拡大して世界中の戦争を終結させる」とエネルギードミナンスを国家戦略の柱の1つとして改めて位置づけています。2024年の共和党政策綱領において、「米国を世界で圧倒的なエネルギー生産国にする」として、化石燃料の生産拡大や、過剰な規制の撤廃、エネルギー生産に関する許認可手続きの効率化が掲げられました。トランプ氏は、国家エネルギードミナンス評議会(National Energy Dominance Council)を新たに設立する大統領令に署名し、議長には内務長官のバーガム氏(元ノースダコタ州知事)が任命されました。同評議会は、米国のあらゆるエネルギー形態の許可・生産・発電・流通・規制・輸送のプロセスを改善することを通じてエネルギードミナンスを達成するための戦略について大統領に助言を行い、また、規制緩和や民間投資の促進、イノベーションの促進を目的とした「国家エネルギードミナンス戦略」を大統領に対して提言する予定です。トランプ第二次政権のエネルギー政策運営上、同評議会が今後担う役割が注目されます。また、「エネルギードミナンス」がどの程度実現されるかは定かではありませんが、この概念が次節以降で示す具体的なエネルギー政策の背景にあることを念頭におく必要があります。
2. 化石燃料の増産・輸出拡大
エネルギードミナンスの追求において、最も重要視されているのが、化石燃料の増産そして輸出の拡大です。 2023年の米国の石油及び天然ガスの生産量は、2000年と比較すると石油は2.2倍、天然ガスは2.0倍と大きく増加しました。ただし、連邦政府所有地が石油・ガス開発に占める割合は低く、現状では石油は12%、天然ガスは9%(2023年)に留まります。
トランプ第二次政権は、「Drill, Baby, Drill(掘って掘って掘りまくれ)」を掛け声に、連邦政府所有地における石油・天然ガス開発を推進すると見込まれます。連邦政府所有地での開発を管轄するのは内務省であり、前述の国家エネルギードミナンス評議会の議長に内務長官が任命されたことは、まさにトランプ第二次政権のエネルギー政策において化石燃料の増産が重要視されていることの証左と言えます。ただ、実は、バイデン政権も連邦政府所有地における開発許認可を速いペースで発給していました。増産推進に向けて規制(連邦政府所有地の開発に関するものや、より一般的な上流開発に関するもの)の緩和が見込まれますが、投資主体となる民間企業による開発申請、ひいては将来的な生産量へ与える影響は限定的となる可能性もあります。
化石燃料の輸出拡大に関連して、バイデン政権は環境基準の見直しを理由に、米国と自由貿易協定を締結していない国へのLNG輸出許可を2024年1月に一時停止しましたが、トランプ氏は就任初日の大統領令において、LNG輸出許可申請の審査を可及的速やかに再開することをエネルギー長官に指示しました。日本は、LNGをトランジションの手段として活用することを見込んでおり、米国は引き続き重要なLNG供給源として期待されます。また、トランプ第二次政権は、第一次と同様に米国の貿易赤字を問題視しており、米国産LNGの購入圧力を高めていますが、日本の中・長期的なLNG需要量は今後のGXの取り組み状況次第で変化すると考えられます。このような状況下で、米国産LNGの販路を日本のみに限らず、アジア市場も視野に入れて需要のアグリゲーションや共同購入などを模索することは、米国にとってはLNG輸出規模の拡大、日本にとっては将来の不透明性への対応と、双方にとって利益をもたらす可能性があります。
3. 環境規制の緩和
環境規制の緩和もトランプ第二次政権のエネルギー関連政策で注目されているテーマの1つです。バイデン政権下で米国環境保護庁(EPA)は、2024年4月に「化石燃料火力発電所からの汚染削減のための規則」を発表しました。同規則は、既存の石炭火力発電所(2039年以降も運転予定のもの)及び新設の天然ガス火力発電所(ベースロード運転のもの)は2032年以降CO2を90%回収することなどを含んだ排出規制です。また、EPAは2023年4月に自動車の温室効果ガス(GHG)排出に関する新たな規制案を発表し、2032年までに新車販売の67%を電気自動車とする基準を策定しました1。トランプ第二次政権では、このような強化された環境規制の緩和(撤廃も含む)が目指されており、2025年3月にはEPAが31に上る規制の見直しを発表しました。この中には、前述の発電所の排出規制の見直しと自動車GHG排出基準の撤廃も含まれています。
また、トランプ氏は電気自動車に関連した国内のサプライチェーンの強化それ自体に否定的ではありませんが、電気自動車の義務化には反対の姿勢を示しており、その方針は共和党政策綱領にも明記されました。IRAにおけるクリーン自動車購入の税額控除(最大7,500ドル/台)は撤回され、電気自動車の普及は停滞する可能性があります。その一方で、重要鉱物やバッテリー製造など電気自動車に関連した国内のサプライチェーンの強化に向けた取り組み(例えば、輸入品への関税賦課や規制緩和によるプロジェクト迅速化)は奨励されるとも考えられます。
脚注
1 なお、2024年3月にバイデン政権は乗用車向けの目標(2032年までに新車販売に占める電気自動車の割合を67%とする)を35~56%に引き下げると発表しています。
4. IRA(インフレ削減法)の見直し
2022年8月に成立したIRA(インフレ削減法)の見直しにも注目が集まっています。IRAは10年間で削減する財政赤字分(約7,370億ドル)を原資として、税額控除や補助金などを通じてエネルギー安全保障・気候変動分野に対して3,690億ドルを投じて、さまざまなクリーンエネルギー技術の製造・導入を支援するものです。税額控除が支出全体の7割以上を占めます。
ただ、トランプ第二次政権がIRAを全面的に見直したり撤回したりする可能性は低く、未執行の予算の取り消しや、要件の変更、共和党内で不人気なプログラムの廃止(例えば、前述のクリーン自動車購入の税額控除)といった方法での政策の修正が図られると予想されています。というのは、トランプ第二次政権がIRA自体の修正・撤回をするには、新たな立法措置が必要となり上下両院で法案を可決させる必要がありますが、共和党議員からすら見直し・撤回に反対が出ているからです。2024年8月には共和党議員18名がIRAの全面撤回に反対する書面を下院議長に提出し、IRAの税額控除によって促進されたエネルギー分野の成長を損なう可能性があるとして、クリーンエネルギー税額控除を廃止しないよう求めています。これは、共和党議員の支持者が多い地域もIRAの投資支援の恩恵を受けていることが背景にあります。
トランプ第二次政権では、就任初日の大統領令で、すべての連邦機関に対してIRAやインフラ投資雇用法に基づく資金支出を直ちに一時停止し、90日以内に見直し結果を国家経済会議(NEC)と行政管理予算局(OMB)へ提出するよう求めています。
バイデン政権下では、日本のGX推進法と米国のIRAとのシナジーの向上に向けた政府間の協議が開始され、取り組み例としてIRAを活用して米国で製造された水素及びその派生品の日本への輸出が挙げられていました。今後、水素についても支援のあり方が見直される可能性があります。IRAではクリーン水素(再生可能エネルギー電力を用いて製造される「グリーン水素」や、化石燃料を用いて製造されるもののCO2を回収・貯留するなどして排出量を実質ゼロにした「ブルー水素」など)の生産税額控除と投資税額控除(ライフサイクルGHG排出量に応じて税額控除額が決定)、またCCUSの導入を支援する税額控除を創設しています。バイデン政権では2025年1月に水素の税額控除に関する最終規則が発表され、グリーン水素のみならず他由来の水素についても、より高い税額控除を申請しやすくなるよう改訂されました。トランプ第二次政権下でこの最終規則が影響を受けるかどうかは不透明であるものの、仮に残る場合はさらに要件を緩和して税額控除を利用しやすくする可能性もあります。
5. 再生可能エネルギー・原子力
トランプ第二次政権では、再生可能エネルギーに対する支援(例えば、IRAの税額控除)が縮小される可能性が高いと考えられます。洋上風力発電については、トランプ大統領が批判的な姿勢をとっており、連邦政府が送電線建設や海域利用の認可権限を有することから開発を阻止あるいは停滞させることが可能です。就任初日には、洋上風力に対する沖合大陸棚のリースを2025年1月21日から覚書が取り消されるまで撤回するという大統領覚書が発表されました。また、太陽光発電については、中国を念頭に太陽光パネルの輸入に対して厳しい追加関税を課すことで、プロジェクトの開発が停滞する可能性があります。このように連邦レベルでは風力や太陽光などの再生可能エネルギーの開発支援があまり期待できないことから、州レベルでの取り組みが進むと考えられます。現在、全米で29州及びコロンビア特別区が再生可能エネルギー利用割合基準(RPS)を導入し、16州がクリーン電力基準(CES)100%の目標(ほとんどはRPSも導入)を掲げ、野心的な州は目標を引き上げる傾向にあります。トランプ第二次政権下は、州ごとの取り組みの差が拡大する期間となると予想されます。なお、RPSやCES100%の目標は、大統領選挙で民主党を支持する傾向の州で多く導入されていますが、共和党支持の州でも導入されています。
原子力については超党派での支持があり、直近では2024年6月に「クリーンエネルギーの多用途かつ先進的な原子力展開の加速化法(ADVANCE法)」が成立しました。同法は、原子力分野における米国のリーダーシップの促進や、新たな原子力技術の開発・展開の支援、米国の核燃料サイクル及びサプライチェーンの強化、原子力規制委員会の効率性向上が規定されています。共和党政策綱領でも、「原子力を含むすべてのエネルギー源からの生産を開放」と明記され、原子力に対する支持はトランプ政権においても継続すると見込まれます。データセンターによる電力需要の拡大を満たすため、原子力発電の中・長期的な貢献が期待される中で、閉鎖済みの原子力発電所の再稼働2 や新設プロジェクト(小型炉、大型炉)の具体的な進展が注目されます。
脚注
2 例えば、パリセード原子力発電所(2022年5月に恒久閉鎖、PWR)、デュアン・アーノルド発電所(2020年8月に恒久閉鎖、BWR)で再稼働が検討されています。また、スリーマイルアイランド原子力発電所1号機は2024年9月に運転再開を決定し、規制当局への手続きを開始しました。
なお、本稿では詳細を取り上げませんでしたが、トランプ第二次政権では、税率は異なるもののすべての国からの輸入品に追加関税を課すと発表し、すでに複数の国・地域との間で対抗措置の応酬が続いています。追加関税が賦課される場合の米国エネルギー事業者の供給コストへの影響や、エネルギー貿易フローの変化、他国から対抗措置が課された場合の米国経済、エネルギー需要への影響は、日本も注視する必要があります。
執筆者プロフィール
下郡 けい
(一財)日本エネルギー経済研究所 資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット 主任研究員
