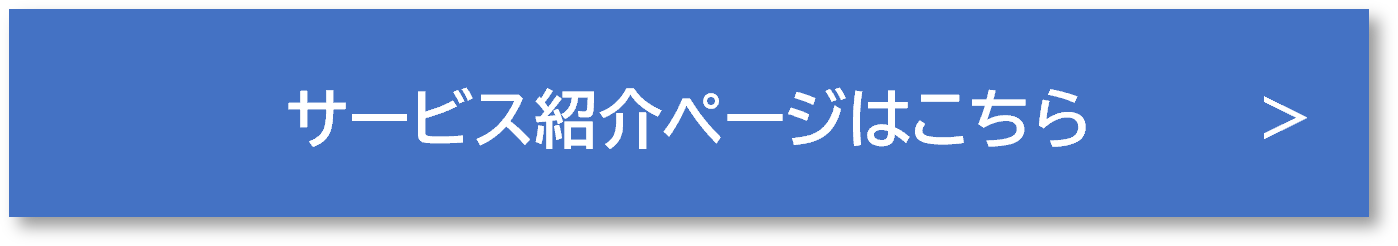企業に求められる人権リスク対策② ~2020年の最新動向~
- 経営・マネジメント
- コンプライアンス
- 人的資本・健康経営・人事労務

2020/12/15
目次
- 日本における「ビジネスと人権」に関する動向
- 欧州における「ビジネスと人権」に関する動向
- 企業人権ベンチマーク
- おわりに
企業に求められる人権リスク対策② ~2020年の最新動向~- リスクマネジメント最前線PDF
執筆コンサルタント
坪井 千香子
製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 上級主任研究員
(専門分野:ESG・サステナビリティ)
谷口 繭
製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 主任研究員

佐藤 美沙紀
製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 研究員
~2020 年の最新動向~
昨今、企業の人権への対応にますます関心が高まっている。企業と人権については、2011年に国連人権理事会が決議した国連「ビジネスと人権に関する指導原則」[1](以下、「指導原則」という)において、「人権を尊重する企業の責任」が明示されており、指導原則に基づく取組が求められているが、これに加えて、近年の ESG 投資[2]への関心の高まりを背景として、企業のESGの取組が注目されており、企業評価の指標の一つとして、S(社会)の分野への取組が注目されるようになってきたことも要因となっている。
2019年1月に発行した「企業に求められる人権対策」[3]では、企業にとっての人権リスクを中心に述べたが、本稿では、2020年に起きた企業と人権に関する国内外の主要なトピックスについてまとめ、今後企業に求められるビジネスと人権への取組について解説する。
1. 日本における「ビジネスと人権」に関する動向
(1)日本の「ビジネスと人権」に関する行動計画の概要
2020年10月16日、日本政府は、ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議において、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020 - 2025)」[4](National Action Plan on Business and Human Rights:以下、「NAP」という)を策定した。NAP とは、前段で触れた「指導原則」を実践するための手段として、国連ビジネスと人権作業部会[5]が各国政府に策定を推奨する行動計画を指す。本項では、日本における NAP 策定に至る背景および NAP の概要について解説する。
各国は、国連ビジネスと人権作業部会が策定した NAP ガイダンス(Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights)[6]を基に NAP の策定作業を進めており、2020年12月1日時点で日本を含む25か国が NAP を策定・公表済み、17か国が策定作業中である[7]。日本においては、2016年に NAP の策定を決定し、約4年の歳月を経て公表に至っている。日本におけるNAP策定の主な過程を表1 に、2019年7月に前述の関係府省庁連絡会議が特定した、特に重点的に検討する必要がある14の事項を表 2 にそれぞれまとめた。
| 年月 | 出来事 |
| 2016年11月 | 第5回国連ビジネスと人権フォーラムにおいて、数年以内に日本のNAPを策定することを日本政府として表明。 |
| 2018年6月 | 閣議決定された「未来投資戦略2018-Society5.0』『データ駆動型社会」への変革-」において、企業行動の原則としての人権の尊重に係る国別行動計画を策定し、企業に先進的な取組を促す旨を明記。 |
| 2018年12月 | 企業活動における人権保護に関する日本の法制度や施策等の現状を調査した「ビジネスと人権に関するベースラインスタディ報告書」を公表。 |
| 2019年4月 | NAP策定に向けて、有識者からの見解を示す諮問委員会およびさまざまな関係者が集まり意見交換を行う作業部会を設置。 |
| 2019年7月 | NAP策定の上で検討する全体的な優先分野5つ[8]と特に重点的に検討する必要がある14の事項を特定(表2を参照)。 |
| 2020年2月 | NAPの原案を公表し、意見を募集。 |
| 2020年10月 | ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議においてNAPを策定、公表。 |
| 出典:外務省ウェブサイト[9]をもとに弊社作成 | |
| 政府組織による人権保護の義務及び人権尊重の推進 | |
| ■公共調達 | ■開発協力・開発金融 |
| ■経済連携協定 | ■人権教育・啓発 |
| 人権を尊重する企業の責任 | |
| ■国内外のサプライチェーンにおける取組 | |
| ■指導原則に基づく人権デュー・ディリジェンスの促進 | |
| ■中小企業における「ビジネスと人権」への取組みに対する政府による支援 | |
| 救済のアクセス | |
| ■司法的救済 | ■非司法的救済 |
| 横断的な事項 | |
| ■労働(ディーセント・ワーク[10]の促進) | ■児童の権利の保護・促進 |
| ■新しい技術の発展に伴う人権(プライバシーの確保、インターネット上の侵害等) | |
| ■ 消費者の権利・役割 | ■法の下の平等(障害者、女性、LGBT、外国人等) |
| 出典:ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議 「ビジネスと人権に関する我が国の行動計画(NAP)の策定に向けて」(令和元年7月)をもとに弊社作成 |
|
公表されたNAPでは、表2の14の事項について、1)人権を保護する国家の義務に関する取組、2)人権を尊重する企業の責任を促すための政府による取組、3)救済へのアクセスに関する取組の3つの観点と、これらの複数の観点による横断的事項を基に、分野別行動計画を策定している。分野別行動計画には、各事項について「既存の制度・これまでの取組」と「今後行っていく具体的な措置」が記載されており、後者については取組を推進する担当府省庁が明記されている。
例えば、アメリカ国務省による人権報告書において「人身取引およびその他の労働者虐待の温床になりやすい」[11]と評価されるなど、国際社会から批判を受けている外国人技能実習制度は、横断的事項として「労働(ディーセント・ワークの促進等)」でカバーされている。政府はNAPにおいて、外国人技能実習制度に関するこれまでの取組として、2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」などによって、技能実習制度の適正化や技能実習生の保護を図ってきたとしている。今後は、技能実習生への人権侵害の禁止規定や人権侵害を行った監理団体等への罰則規定の整備、技能実習生が母国語で相談できる窓口の設置などについて、法務省、外務省および厚生労働省が引き続き取り組むとしており、技能実習制度の改善を着実に進めることが期待される。
それでは、NAPは企業にどのような影響を与えるのだろうか。企業に求められる対応については、NAPの第3章「政府から企業への期待表明」に示されている。政府は規模や業種等にかかわらず全ての日本企業に対し、1)国際的に認められた人権及び「労働における基本的な原則及び権利に関するILOの宣言」[12]に述べられている基本的権利に関する原則を尊重し、「指導原則」などの国際的なスタンダードに則って人権デュー・ディリジェンス[13]のプロセスを導入すること、2)サプライチェーンを含むステークホルダーとの対話を実施すること、3)効果的な苦情処理の仕組みを通じた問題解決を図ることを「期待する」としている。「期待する」という文言は決して強い表現ではないが、本稿第2章で述べるように、欧州では人権デュー・ディリジェンスが義務化されるなど、「ビジネスと人権」に関する取組が強化されていることから、日本企業においても、今後の規制強化を見据えつつ、人権対応の体制整備や現状把握に取り組み、「指導原則」などの国際基準による要求事項を実施していくことが求められる。
(2)日本の「ビジネスと人権」に関する行動計画の今後
NAPは、NAPガイダンスにおいて「進化する政策戦略(evolving policy strategy)」と定義されている通り、策定を以って人権に関する取組が完了するものではなく、取組の有効性を検証した上で定期的にNAPをアップデートしていくことが重要である。日本のNAPは行動計画の期間を2020~2025年度の5年間と定め、公表4年後を目処にNAPの改定作業に着手することが示されている[14]。
NAPガイダンスは、NAPの作成から実行、アップデートの全ての過程で、関係するステークホルダーの意見を考慮しながら包括性かつ透明性のある作業を進めていくことを求めている。日本のNAP策定過程においても、ベースラインスタディの段階で、経済界や労働界、市民社会等のステークホルダーと関係府省庁との意見交換を計10回実施した[15]。意見交換に参加した団体は、2019年4月に設置された作業部会にも引き続きステークホルダーの立場から参加しており、ステークホルダーとして意見が一致する項目について、NAPに反映させるべき共通要請事項として計2回にわたり公表している。NAPの策定後に作業部会のステークホルダー構成員が発表した合同コメントでは、NAPにおいて既存の施策の整理と今後取るべき措置について担当府省庁を明記した点を歓迎する一方、ステークホルダー構成員からの要請事項の反映が不十分であるとして、引き続き「ステークホルダー関与型のNAP実施・モニタリング・改定の体制整備」の仕組みの具体化を要請している[16]。
イギリスやスイスにおいては既にNAPの第2版が策定済みであり、スイスの第2版においては、連邦政府や企業、市民社会、学界などの代表者からなるモニタリンググループが各ステークホルダーグループの窓口となり、ステークホルダーの意見が適切に考慮されることを確認するとしている[17]。日本のNAPにおいても、NAP策定後速やかに関係府省庁とステークホルダーの継続的な対話を行うための仕組みを立ち上げるとされていることから、日本政府においては、ステークホルダーの意見を十分に取り入れることができる体制の構築が期待される。
2. 欧州における「ビジネスと人権」に関する動向
(1)欧州各国における取組
前章では日本のNAPに関する動向を解説したが、海外ではどのような取組が行われているのだろうか。本章では、人権に関する取組が先行している欧州の動向を解説する。
NAP策定済みの25か国のうち、欧州地域が18か国と大半を占めており、前述の通りイギリスやスイスなど、初期にNAPを策定した国では既にNAPの第2版が公表されている。欧州では、NAPの策定以外にも各国独自の法規制によって企業によるサプライチェーンにおける人権への取組を促進する動きが活発化しており、その概要を表3にまとめた。
| 国 | 概要 |
| イギリス | 2015年に「現代奴隷法」を制定。現代における強制労働や人身取引について規定しており、イギリスで事業活動を行う一定以上の売上高のある国内外の企業は、毎年、サプライチェーンにおける奴隷や人身取引に関する情報を記載した報告書の作成・公開が求められる。今後、企業による情報開示を強化するために法律を改正する予定[18]。 |
| フランス | 2017年に「企業注意義務法」を制定。本社所在地によって従業員数の基準は異なるが、従業員数が一定以上の国内外企業に対し、事業活動による人権侵害や環境破壊などに関するリスクの特定・防止を求める。対象企業にはリスクマッピングやリスクの軽減方法等を記載した報告書の作成・公開の義務があり、違反した場合、金銭的な強制力を伴う処分が下される場合がある。 |
| オランダ | 2019年に「児童労働デュー・ディリジェンス法」を制定。オランダで事業活動を行う国内外の企業に対し、18歳未満の児童による労働を伴う商品やサービスの提供を防止するデュー・ディリジェンスを実施していることを宣言させ、疑いのある場合にはアクションプランの作成・実行を求める。違反した場合には罰金刑となる。 |
| 出典:各法律および NGO 等によるその英訳[19]をもとに弊社作成 | |
上記以外にも、ドイツやスイスなどでは人権デュー・ディリジェンスの義務化に向けた動きがある。例えばドイツでは、連邦政府が2016年に策定したNAPにおいて、2020年までにドイツに拠点を置く従業員数500人以上の企業のうち、50%以上が人権デュー・ディリジェンスの要素を企業のプロセスに導入しなかった場合、立法措置を取ることを示唆していた[20]。しかし、NAPの最終年として2020年10月に公表された最終モニタリングレポートでは、NAPの要求事項を遵守した企業は対象企業の13%~17%であったとされている[21]。設定された目標は企業の自主的な取組だけでは未達成となったことから、今後ドイツでも一定規模以上の企業に対して人権デュー・ディリジェンスが義務付けられる可能性が高いと考えられる。
欧州以外にも、オーストラリアの「現代奴隷法」やアメリカのカリフォルニア州の「サプライチェーン透明法」が「ビジネスと人権」に関連する法律として制定されている。今後も各国によるこのような取組が拡大すれば、人権デュー・ディリジェンスの義務化が国際的なスタンダードとなる可能性もあるため、グローバル企業におかれては、現地における動向を注視していく必要がある。
(2)EUによる人権デュー・ディリジェンスの義務化
欧州地域には、「ビジネスと人権」に関するもう一つの興味深い動きがある。それは、欧州連合(以下、「EU」という)による人権デュー・ディリジェンスの義務化である。欧州域内では、前項で解説した加盟国レベルでの取組に加えて、大企業に対して環境や社会、雇用等の非財務情報の開示を義務付ける2014年の「非財務情報開示指令」[22]や、紛争地域および高リスク地域から特定の鉱物を調達する企業に対してサプライチェーンデュー・ディリジェンスの実施と報告を義務付ける2017年の「紛争鉱物規則」[23](2021年1月より全面適用)など、企業に対して人権への対応を義務化する動きを加速化してきた。
このような流れの中、2020年4月、欧州委員会の司法長官は欧州議会の作業部会によるウェビナーの中で、2021年に向けてEU法として企業による人権および環境デュー・ディリジェンスを義務化させることを明言した。司法長官はスピーチにおいて、デュー・ディリジェンスに関する意識調査の結果、公平な競争や第三国のサプライチェーンへの影響力を高めることにつながることから、企業調査では回答者の7割がEUによるデュー・ディリジェンスの義務化がビジネスにとって有益であると回答しているとも述べている[24]。この発言を受けて、2020年9月には、アディダスやユニリーバといった26の企業が共同声明を発表し、司法長官の発表を歓迎すること、そして企業としてEUのリーダーシップを支援していくことを表明した[25]。このように、欧州においては企業以外にも、投資家や労働組合、市民団体などからEUあるいは各国政府に対して、人権デュー・ディリジェンスの義務化を求める声が多く上がっている。
EUは既に法律の制定に向けて動き始めている。2020年9月11日、欧州議会の法務委員会は欧州委員会に対して、人権および環境デュー・ディリジェンスに関する法案の提出を勧告したドラフトレポートを提出した[26]。レポートには法案が添付されており、1)対象企業はEUを拠点とするあらゆる企業およびEU域内で事業活動を行うEUを拠点としない企業とする、2)企業に事業活動に伴う人権・環境およびガバナンスリスクに関するデュー・ディリジェンスを義務付ける、3)一次サプライヤーに限らず全てのサプライヤーをデュー・ディリジェンスの対象とする、4)救済へのアクセスの確保、5)罰則規定の導入等が記載されている。
現在、欧州委員会では、人権デュー・ディリジェンスの義務化を含めた持続可能なコーポレートガバナンスについて、オンラインでのパブリックコンサルテーションを実施している(2021年2月8日まで)。今後、EUにおける通常の立法手続きに則り、EU指令として成立した場合、加盟各国における国内法の制定および実施体制の整備が進められることとなる。企業には、本章で解説したような海外の動向も把握し、単なるコンプライアンスの一環としてのみならず、企業価値向上やサプライチェーンとの関係強化につながる取組として、自社の事業活動とリンクした人権対応を積極的に推進することが期待される。
3. 企業人権ベンチマーク
(1)企業人権ベンチマークの 2020年結果
企業の人権に関する取組を公開情報に基づいて評価し、2017年から結果を公表している企業人権ベンチマーク[27](Corporate Human Rights Benchmark:以下、「CHRB」という)は、2020年11月16日に2020年の結果を発表した[28]。評価の対象となる業種は、2017年および2018年には農作物、アパレル、資源採掘のみであったが、2019年からICT関連製造業が加わり、2020年には新たに自動車産業が追加された。評価対象企業は世界の時価総額上位企業の中から選ばれ、企業数は2017年の98社から年々増加し、2020年には229社へと拡大した。日本企業は2017年、2018年と2社のみが評価対象であったが、2019年には18社、2020年には27社が評価対象となった。
CHRBの評価では、「指導原則」に基づき、6つのテーマ(A.ガバナンスと方針によるコミットメント、B.人権尊重と人権デュー・ディリジェンスの組み込み、C.救済と苦情処理メカニズム、D.人権に関する取組、E.深刻な申し立てへの対応、F.透明性)に関して設けられた各指標の獲得スコアを基に総スコアが導き出される。なお、2020年の評価では新型コロナウイルスの影響を鑑み、6つのテーマ全てに関する評価が実施されたのは自動車産業のみであり、自動車産業以外の4業種については3つのテーマ(上記のA.B.C.)に関する13の指標(CHRB Core UNGP[29] Indicatorsと呼ばれる)で評価が実施された。以下では、2020年に新たにCHRBの評価対象となった自動車産業の結果と、自動車産業を含めた評価対象業種全体の結果について概要を紹介する。
□自動車産業の結果
自動車産業の評価対象企業30社の平均スコアは100点満点中12点であり、過去にCHRBが評価した業種の中で最も低い数字であった。評価対象となった30社のうち50点以上を獲得した企業は無く、半数の企業が10点未満であった。最も高い点を獲得したのは41.5点のフォード・モーターであり、次いで33点のグループPSA、30.6点のダイムラーであった。日本企業は7社が評価対象となり、4社が10~20点の範囲、3社が0~10点の範囲という結果であった。CHRBは、自動車産業全体において指導原則の実行が不十分であることを今回の結果が示唆していると述べている。
自動車産業で特に改善が必要な分野としてサプライチェーンの管理が挙げられており、評価対象企業の9割でサプライチェーンにおける強制労働や児童労働、結社の自由や団体交渉権等の人権リスクへの対応状況が開示されていないとされた。また、大半の企業において、強制労働や児童労働の防止、労働組合員や労働組合の代表への脅迫又はハラスメントの防止に関するサプライヤーとの協力、又は契約の取り決めが確認できなかった。なお、ゼネラルモーターズは30社の中で唯一、主要部品の製造拠点を含む直接・間接サプライヤーのマッピングを実施していることが確認された。
評価対象となった自動車産業の30社は、World Benchmark Alliance(WBA)[30]が開発したClimate and Energy Benchmarkで気候変動対策についても評価されたが、人権と気候変動双方の評価結果から相関関係はほとんど見られなかった。例えば、低炭素移行計画や温室効果ガス排出削減目標が策定され、気候変動対策に関するガバナンスが実施されている企業であっても、人権への取組状況が開示されているとは限らなかった。自動車市場では今後、電気自動車の普及拡大が見込まれるが、電気自動車のバッテリーに使用されるコバルトの採掘に関しては、児童労働を含む人権侵害が懸念されている[31]。アメリカでは、コンゴ民主共和国でのコバルト採掘で児童労働を支援したとして人権保護団体が電気自動車メーカーを含む大手企業5社を提訴した例もある[32]。今後数十年の間に、自動車産業が脱炭素経済への移行という大きな課題に直面する中、企業が気候変動と人権双方の領域で成果を示すことは公正な移行[33]を実現するために最も重要であるとCHRBは説明している。
□全体の結果
2020年の評価では、自動車産業以外に農作物企業57社、アパレル企業53社、資源採掘企業57社、ICT関連製造企業44社が評価対象となった。一部の企業は複数の業種で重複して評価されており、4業種で合計199社が評価されている。4業種の平均点はそれぞれ26点満点中、農作物企業が10.3点、アパレル企業が9.0点、資源採掘企業が10.2点、ICT関連製造企業が7.9点であった。各業種で最高点を獲得したのは、農作物企業ではユニリーバ(25点)、アパレル企業ではアディダス(23点)、資源採掘企業ではEni(25点)、ICT関連製造企業ではエリクソン(22点)である。
CHRBによれば、自動車産業を含めた5業種全体で、大多数の企業が人権デュー・ディリジェンスに関する投資家の期待に応えられていない。2019年のCHRB評価において人権デュー・ディリジェンス関連指標の得点が0点であった95社に対し、176の投資家からなる団体(「Investor Alliance for Human Rights」)は2020年3月に早急な改善を求める書簡[34]を送ったが、2020年の評価において人権デュー・ディリジェンスに関する改善が確認できたのは95社中16社にとどまり、79社は今年も当該指標で得点できていなかった。今回初めて評価対象となった自動車産業では、70%の企業が人権デュー・ディリジェンスに関する評価指標で得点できなかった。
一方、昨年に引き続き評価された4業種については改善傾向も確認された。13指標のうち最も改善されたのは、「人権尊重へのコミットメント」と「外部の個人やコミュニティのための苦情処理ルート」の2指標であった。ただし、199社のうち1/3以上の企業は2019年の得点から改善が見られなかった。
CHRBによれば、人権対策の基礎的要件である人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスの実施に関して多くの企業が取組を進めつつあるが、それらの人権方針や人権デュー・ディリジェンスのプロセスと実際に現地で起きている人権への影響の間には懸念すべき乖離が見られている。今回評価対象となった全業種229社のうち、深刻な人権侵害の申し立てを1件以上受けている企業は104社あり、申し立ては全体で225件報告された。これらの申し立てについて、ステークホルダーとのダイアログ[35]を実施したケースは1/3に満たず、被害者が満足できる実効性のある救済措置を講じたケースはわずか4%であった。
また、今回評価された229社のうち78%はOECD諸国に本社がある一方、確認された深刻な人権侵害225件のうち85%が発展途上国で起きている。人権侵害の種類として多いのは強制労働、児童労働、労働安全衛生の違反であり、事案が多く発生しているのはインド(24件)、中国(21件)、インドネシア(19件)であった。ただし、2020年のCHRB評価で確認されたのは2017年から2019年に発生した事案の中でも最も深刻な人権侵害に限られており、今回の評価で捕捉できていない多くの申し立てがあると指摘されている。
(2)企業に求められていること
CHRBの評価においては、「指導原則」を人権尊重の取組の基本的概念としており、企業がサプライチェーン全体にわたって人権尊重の取組を実施することを求めている。指導原則によれば、企業は自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長したりすることを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処することはもちろん、たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品又はサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止又は軽減するように努める必要がある(原則13)。すなわち、バックナンバー「企業に求められる人権リスク対策」[36]でも述べた通り、企業は自社の従業員の人権という狭い範囲ではなく、事業活動を行う上で影響を与える可能性のある地域住民の人権から、サプライヤーや取引関係のある第三者による影響まで、サプライチェーンの広範囲に及ぶ人権を尊重することが求められている。
CHRBの分析は、評価対象となった企業にとって、自社の人権に関する取組のどこに課題があるのかを理解するために有用である。このため、企業は自社の認識とCHRB評価のギャップを埋めるべく、人権尊重に関する方針の策定、体制整備、情報開示等の取組を進め、各業種のリーディング企業から学ぶべきであるとCHRBは説明している。なお、現時点でCHRBの評価対象となっている業種は5つと少ないが、指導原則でも述べられている通り、人権を尊重する企業の責任は、その規模、業種、事業状況、所有形態や組織構造にかかわらず、全ての企業に適用される(原則14)。CHRBの評価対象業種か否かにかかわらず、企業は自社の人権に関する取組状況を評価し、リーディング企業の取組を参考にすることが望まれる。
また、本稿第3章でも取り上げた通り、欧州地域では人権デュー・ディリジェンスを義務化する動きがあるが、今回のCHRB評価では人権デュー・ディリジェンスの実施に関して5業種いずれも不十分であることが明らかになった。CHRBは、人権リスクを認識し、評価し、人権への負の影響を軽減する行動をとるために必要な人権デュー・ディリジェンスのプロセス構築と実施について、企業が迅速に歩みを進める必要があると述べている。
4. おわりに
本稿では、昨今関心が高まっている「ビジネスと人権」について、国内外の動向をまとめるとともに、人権に関する企業評価の結果とそこから得られる示唆についてまとめた。我が国のNAPは、ようやく初版が策定・公表されたばかりであり、企業の取組についても自主性に委ねられている状況であるが、諸外国の動向等を鑑みると、企業リスクの低減および企業価値向上のためにも、その状況に甘んじることなく率先して人権への取組を進めることが望まれる。国内では、人権への取組というと、自社の従業員への対応等に目が行きがちであるが、ビジネスが世界全体につながっている今日、自社のビジネスが世界各国の人権にもたらす影響について認識・把握していないことは、大きな企業リスクとなり得る。まずは、自社のビジネスと人権への影響の関係について、バリューチェーン全体を見渡し、精査してみることが重要である。本稿が、貴社におけるリスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸いである。
[2020年12月15日発行]
参考情報・サービスご案内
執筆コンサルタント
坪井 千香子
製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 上級主任研究員
(専門分野:ESG・サステナビリティ)
谷口 繭
製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 主任研究員

佐藤 美沙紀
製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 研究員
ビジネスと人権に関する取り組み支援